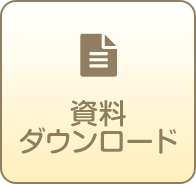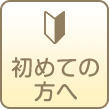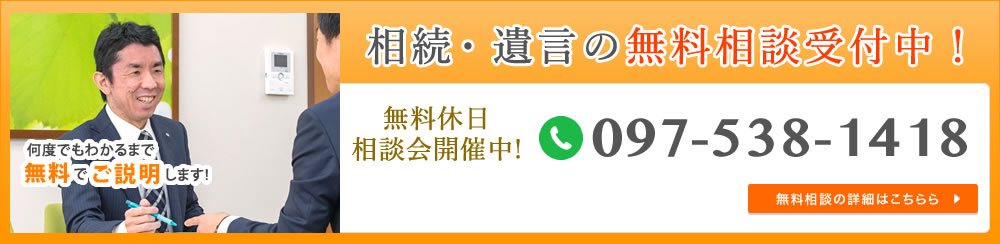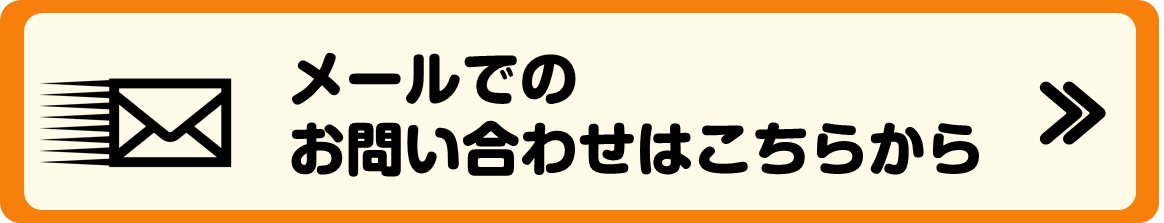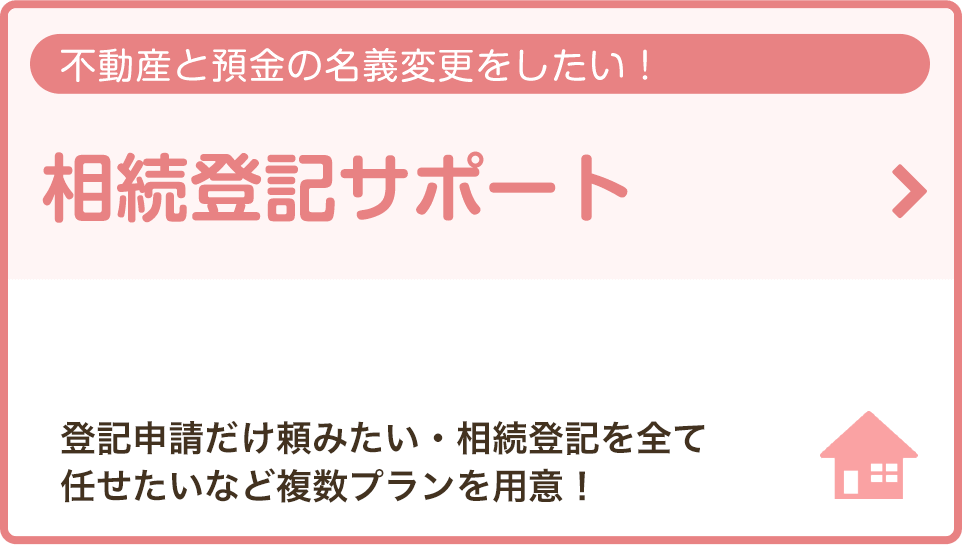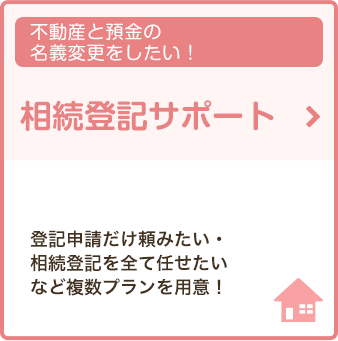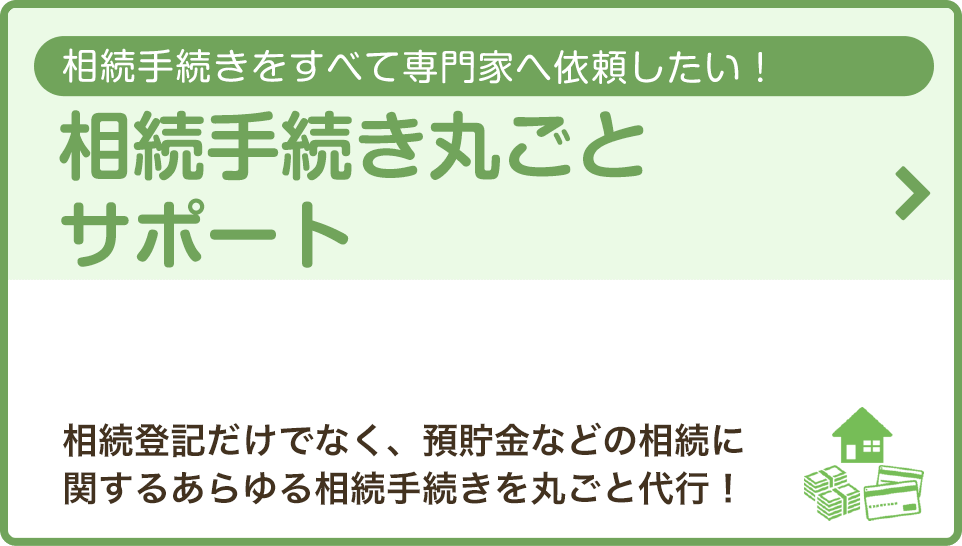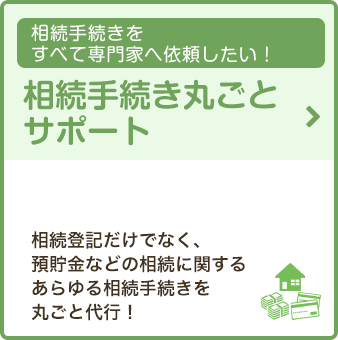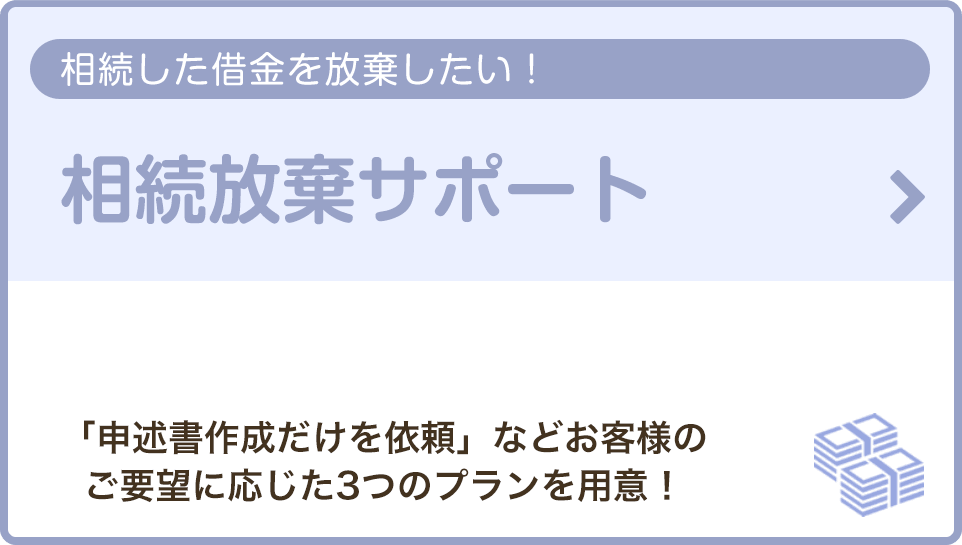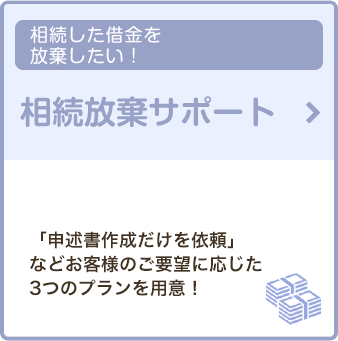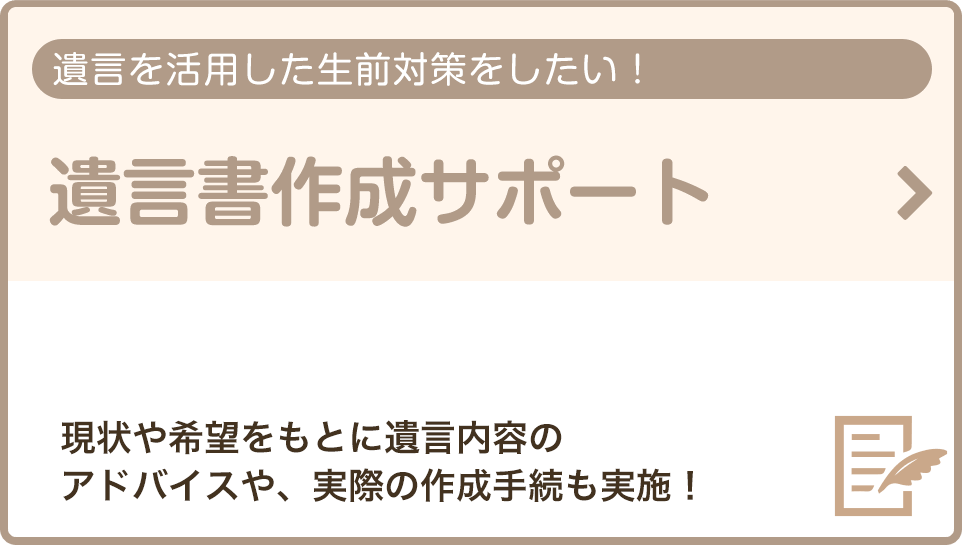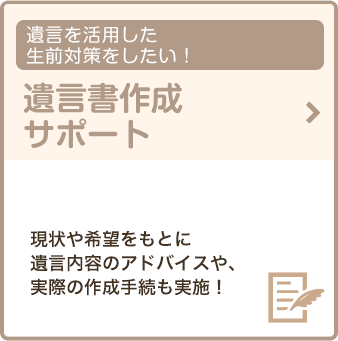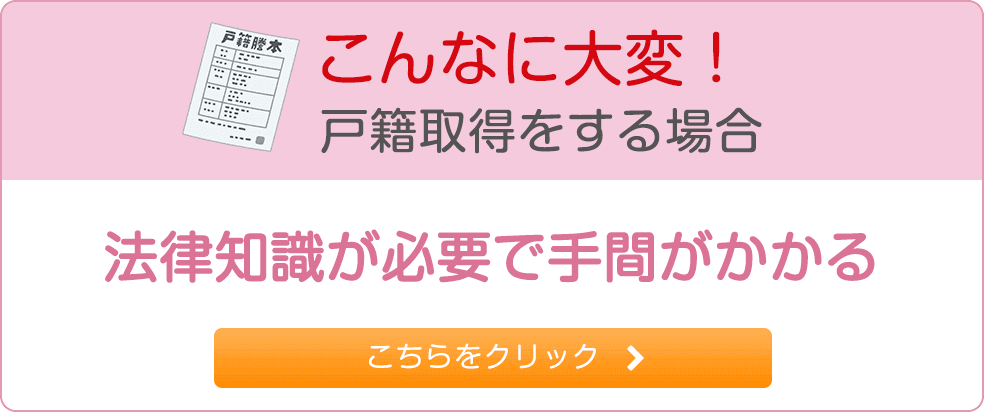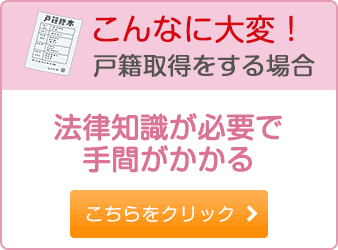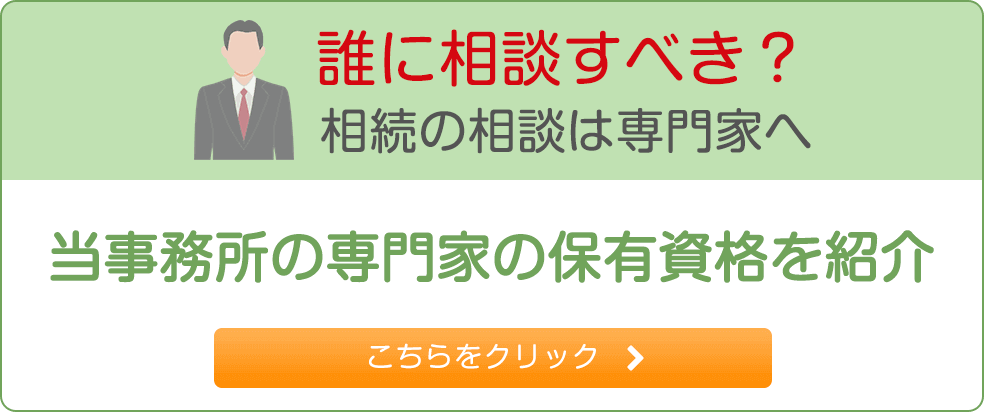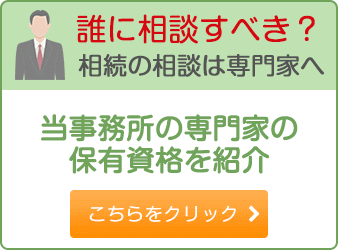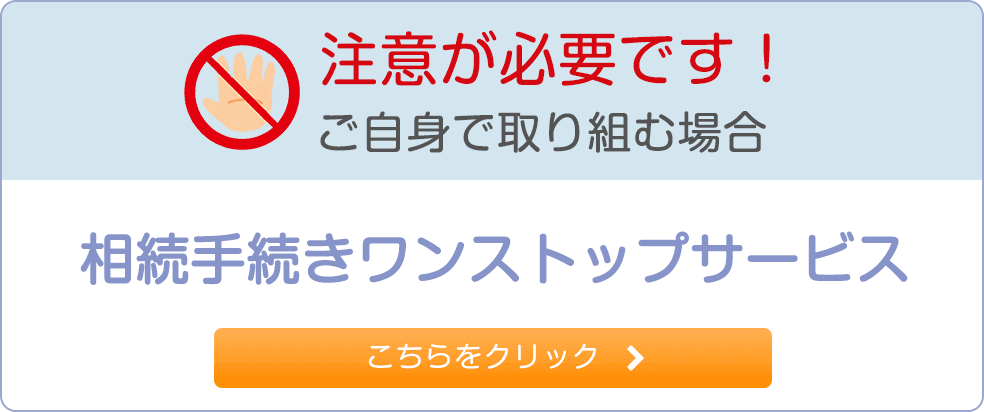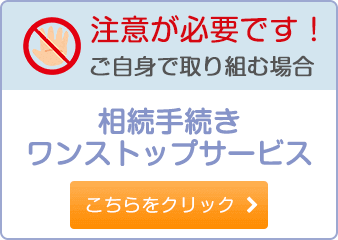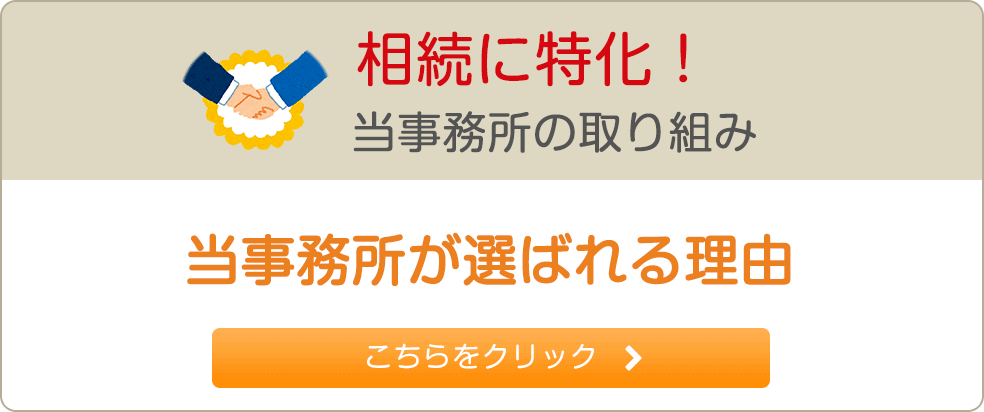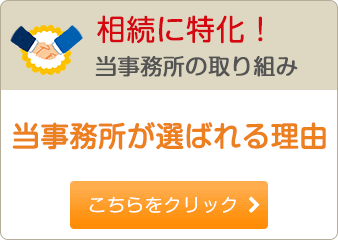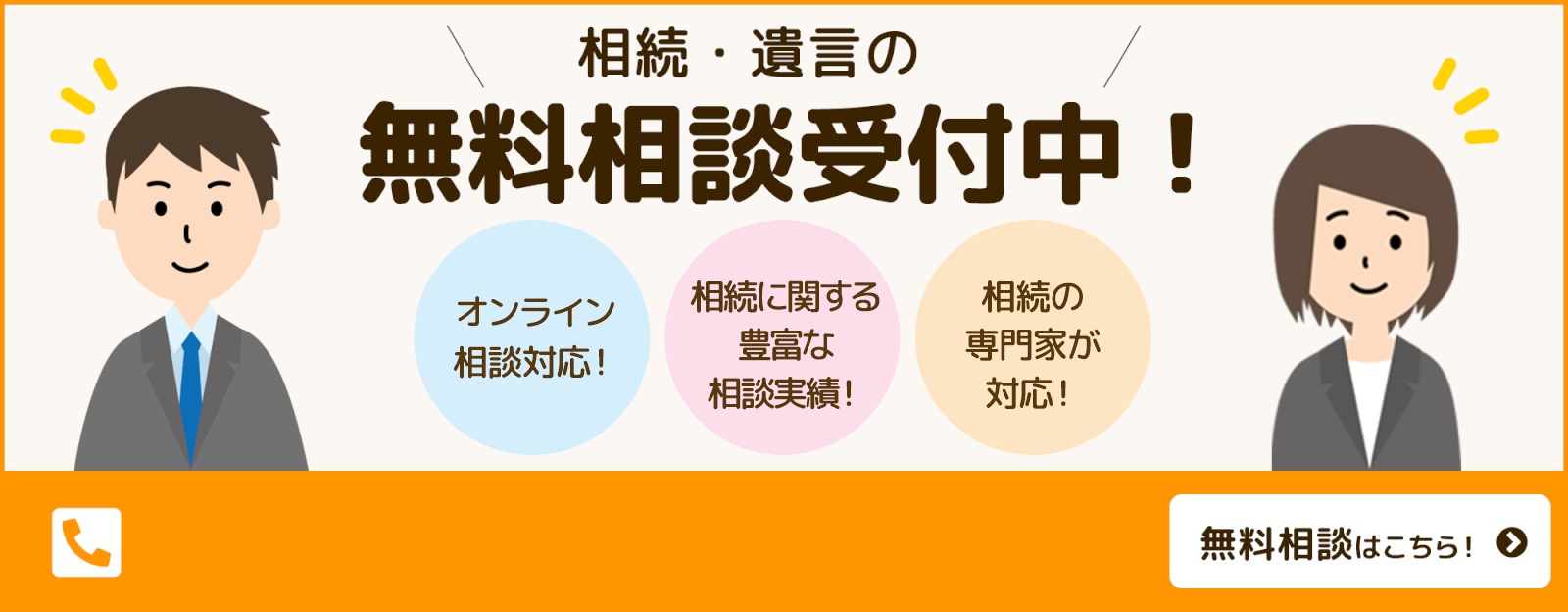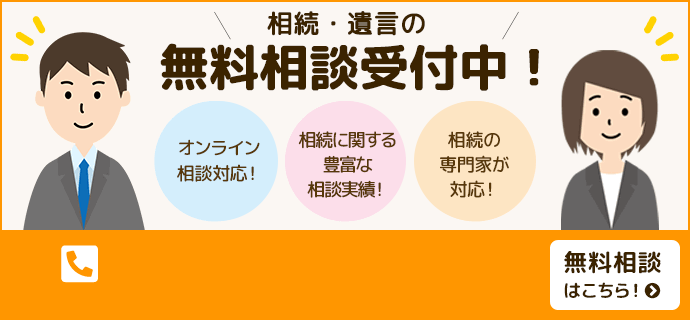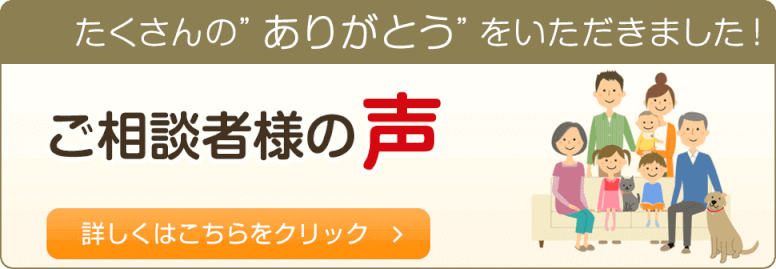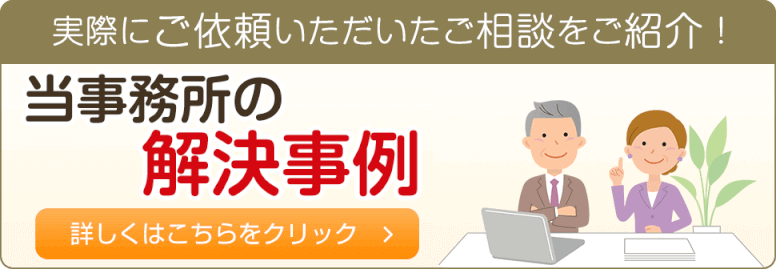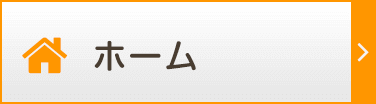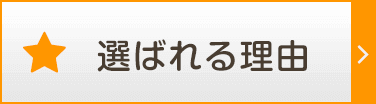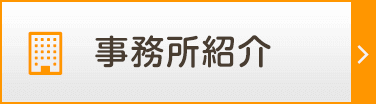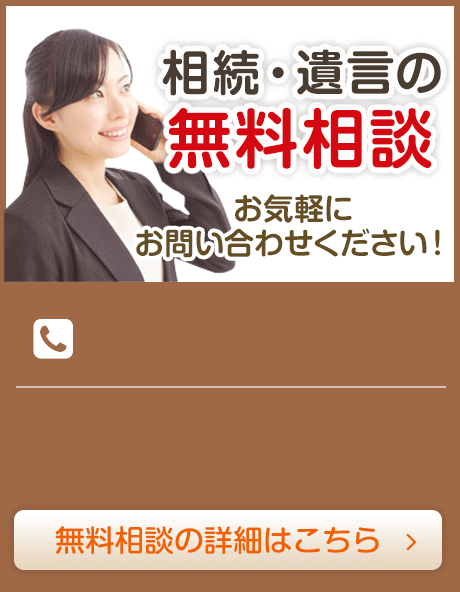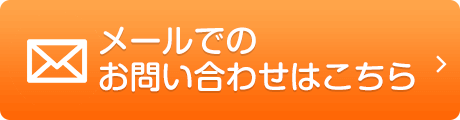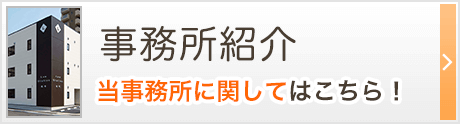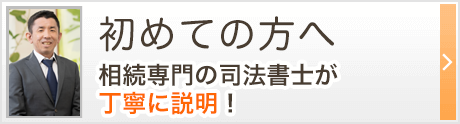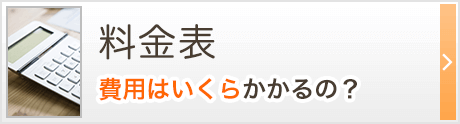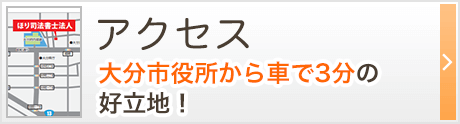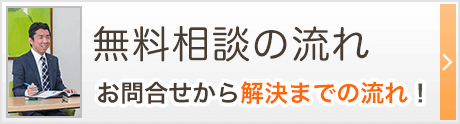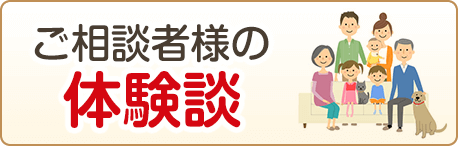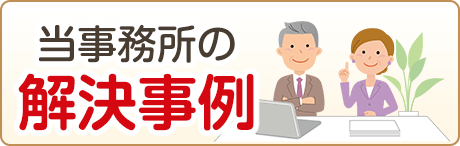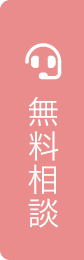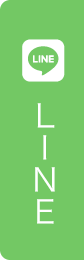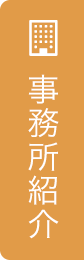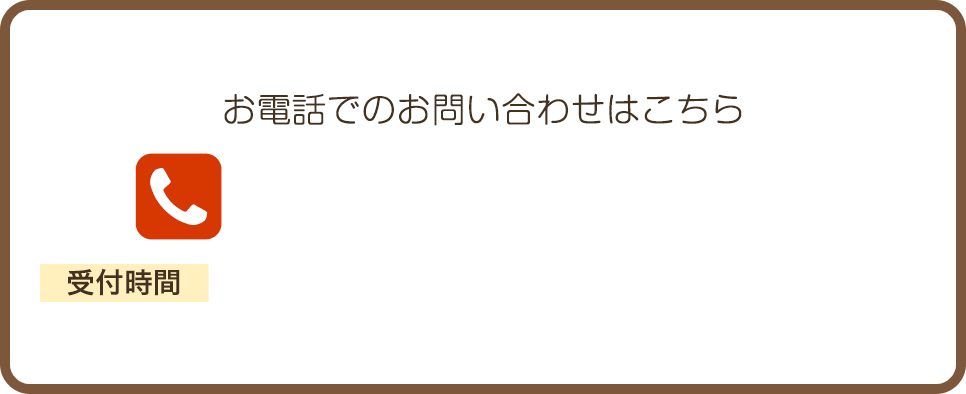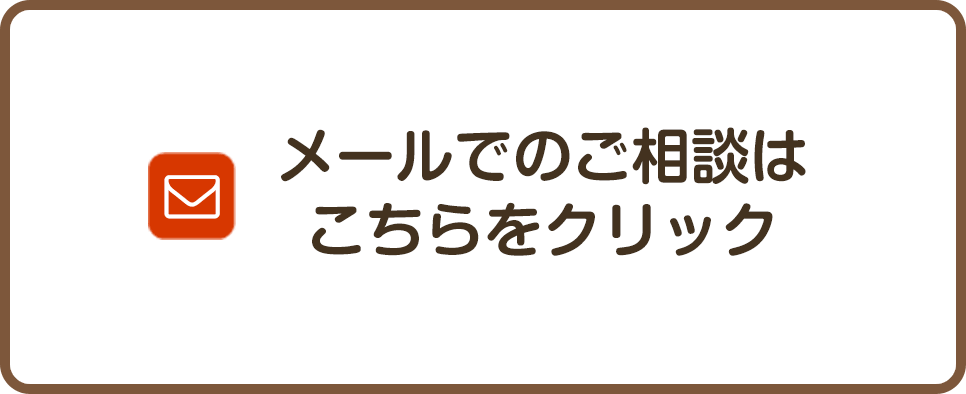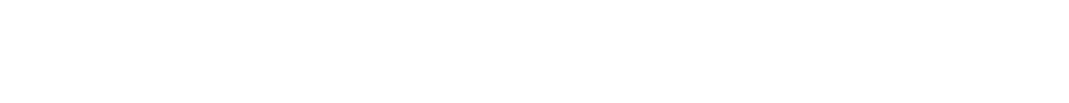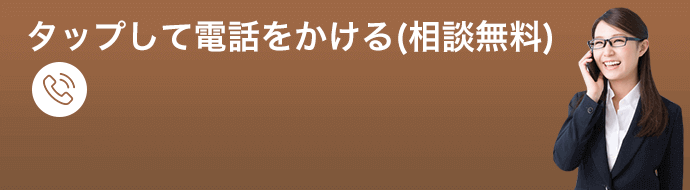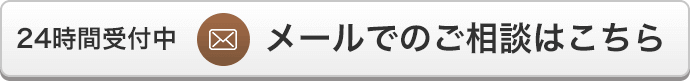判例編2:遺言書を破棄・隠匿したら相続欠格になるか
目次
太郎さんは遺言を書いて息子の一郎さんに渡していました。
その遺言は一郎さんにとっては有利な内容でした。太郎さんが亡くなった後、一郎さんはその遺言を使わず、一郎さんと兄弟の二郎さんは遺産分割協議で相続手続きをしました。
ところが二郎さんは、一郎さんが遺言があるのに使わなかったのは隠匿であり、一郎さんは相続欠格者だと主張したのです。
相続欠格とは?
相続欠格とは、法律上、相続人としての資格を失うことを指します。
相続欠格になると、相続財産を相続することができなくなります。
相続欠格になる理由は、以下のようなものがあります。
1.殺人や暴力行為による相続人殺害罪などの重罪を犯した場合
2・遺産分割協議書や遺言書の作成に際して、相続人を脅迫、恐喝した場合
3・相続財産を隠し、偽装、財産を損壊、破壊した場合
4.準禁錮罪以上の刑に処せられた場合
5.養護責任者に対して相続放棄届を出すことが認められた場合
相続欠格となった場合、相続人としての地位を喪失し、相続財産を相続できなくなるため、財産分割に関する権利や手続きに参加することもできなくなります。
さて、一郎さんは相続欠格者になるでしょうか。
今回も前回と同じく、相続欠格は民法891条に記載されていますが、その5号で、「相続に関する被相続人の遺言を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」とあり、今回のケースに当たるのではないかと推測されます。
しかし、裁判所は、相続欠格になるには、破棄・隠匿が故意に行われ、不当な利益を得る目的や動機が必要であるとして、「二重の故意」が必要だと判断しました。
今回のケースでは、遺言を使えば一郎さんはもっと有利に相続できたはずなのに、遺言を使わず遺産分割協議をしたこと、遺言は破棄・隠匿ではなく紛失してしまったことから、二重の故意にはあたらず、相続欠格者ではない、ということになりました。
せっかく亡くなった方が遺言を残していたのに、相続人がその遺言を使わず遺産分割協議をすることは実務でもたまにありますが、相続欠格になるか否かにかかわらず、相続人全員納得のうえで協議しないといけませんね。
当事務所では、遺言の書き方のアドバイスや公正証書遺言作成のお手伝い、遺言の検認手続き、相続手続きなど幅広く取り扱っておりますので、遠慮なくご相談くださいね。
今回の参照判例:最3判平成9年1月28日民集51巻1号184項
二重の故意の理論とは?
民法891条5号は、相続欠格事由として、遺言書の「破棄、隠匿」という行為を示すのみですが、以下のような事例で、酷な結果を招きます。
そこで、今回の件についての判例では、「二重の故意」の理論を採用しました。
<「破棄、隠匿」という行為だけでみた際の酷な結果>
①自己に対する包括遺贈を記載した自筆証書遺言を、敢えて他の共同相続人に示さず(隠匿して)他の共同相続人が遺留分相当額以上のものを取得するという遺産分割協議を成立させた相続人(遺留分相当額を取得させている点で他の共同相続人の利益を害してはいません。)
②自己に対する包括遺贈を記載した自筆証書遺言書を、法定相続分の取得でよいと考えて破棄した者
そこで、5号については「二重の故意」即ち①遺言書を故意に偽造、変造、破棄又は隠匿することに加え、②自らが相続上有利な地位を得ようとする積極的な動機・目的が必要という見解が有力で、平成9年判決は「破棄、隠匿」の事案について「相続に関して不当な利益を目的とする」かどうかを付け加え判断することで、この「二重の故意」の理論を採用しました。
今回の事例に関する当事務所のサービス
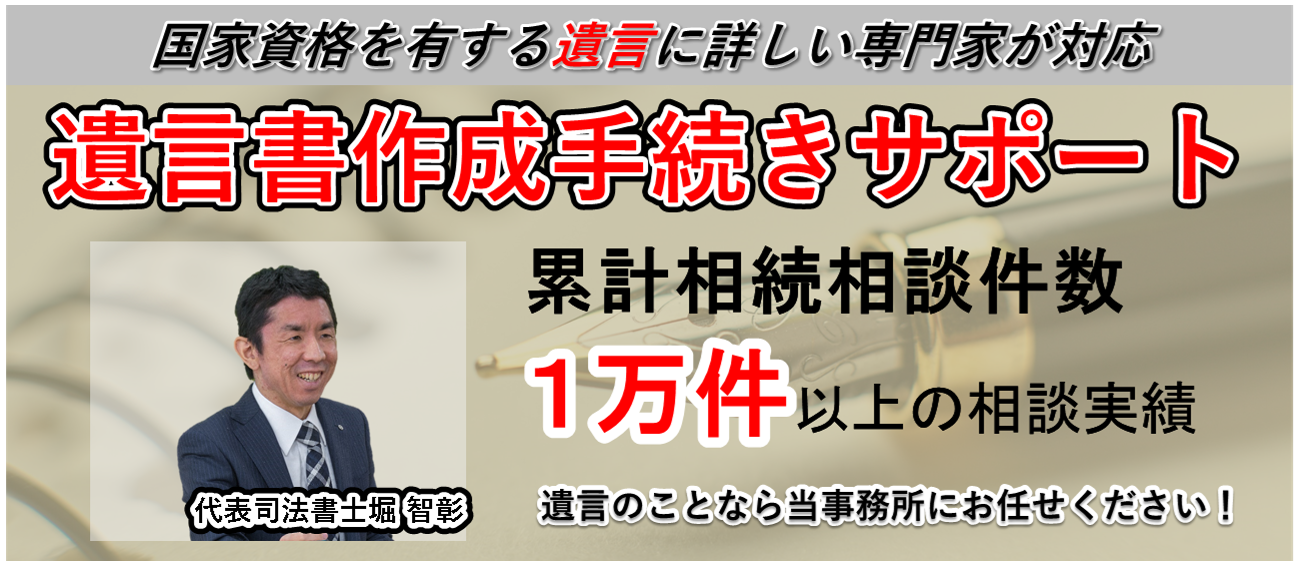
遺言の種類
相続人が遺産を巡り「争族」となることを防止するためには、遺言の作成が効果的です。
遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
遺言の目的によって、自分に相応しいものを選びましょう。
詳しくは、「遺言の種類」をご覧ください。
遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは 097-538-1418 になります。
お気軽にご相談ください。
- 判例編1:相続人が押印した遺言書と相続欠格!?【司法書士が徹底解説!】
- 判例編2:遺言書を破棄・隠匿したら相続欠格になるか
- 判例編3:夫が亡くなり親族と姻族関係を終了したが、祭祀を引き継げるのか?
- 判例編4:占有は相続できるのか?【司法書士が徹底解説!】
- 判例編5:慰謝料の相続
- 判例編6:生命保険と相続
- 判例編7:賃料の相続【遺産分割について司法書士が徹底解説!】
- 判例編8:現金の相続【遺産分割協議について司法書士が徹底解説!】
- 相続財産調査】銀行への取引履歴の開示請求/不動産・預金の調べ方
- 判例編10:婚外子の相続分
- 判例編11:生命保険の特別受益
- 判例編12:相続放棄の熟慮期間の起算点
- 判例編13:成年後見人が特別縁故者になれるのか?【相続のキホンを徹底解説!】
- 判例編14:認知症と遺言
- 判例編15:添え手遺言
- 判例編16:自筆証書遺言の印鑑
- 判例編17:公正証書遺言が無効になる場合を【司法書士が解説】
- 判例編18:共同遺言