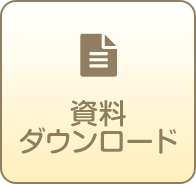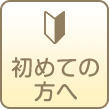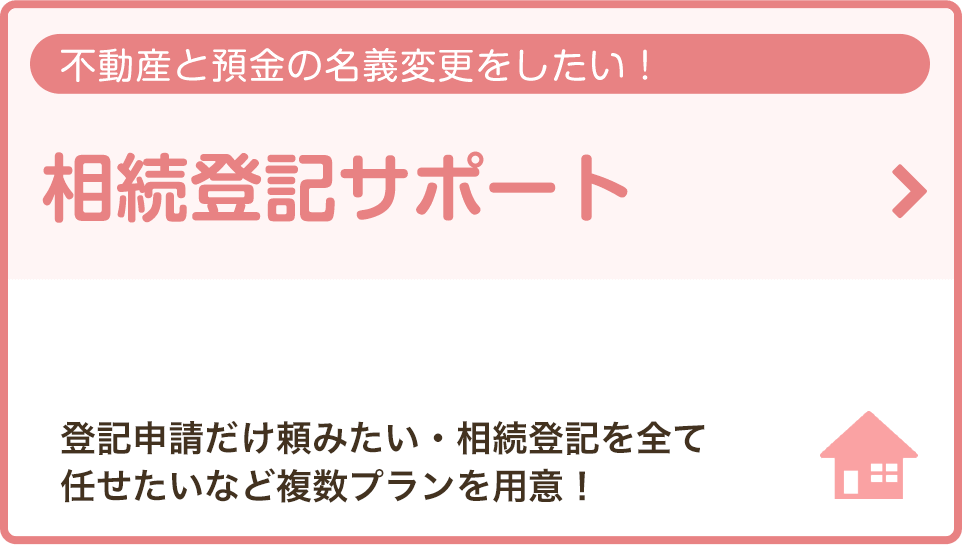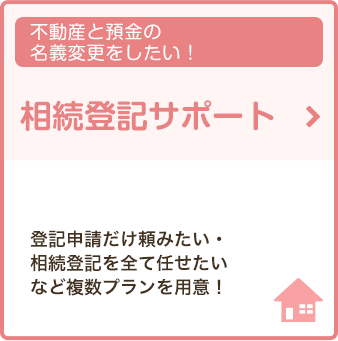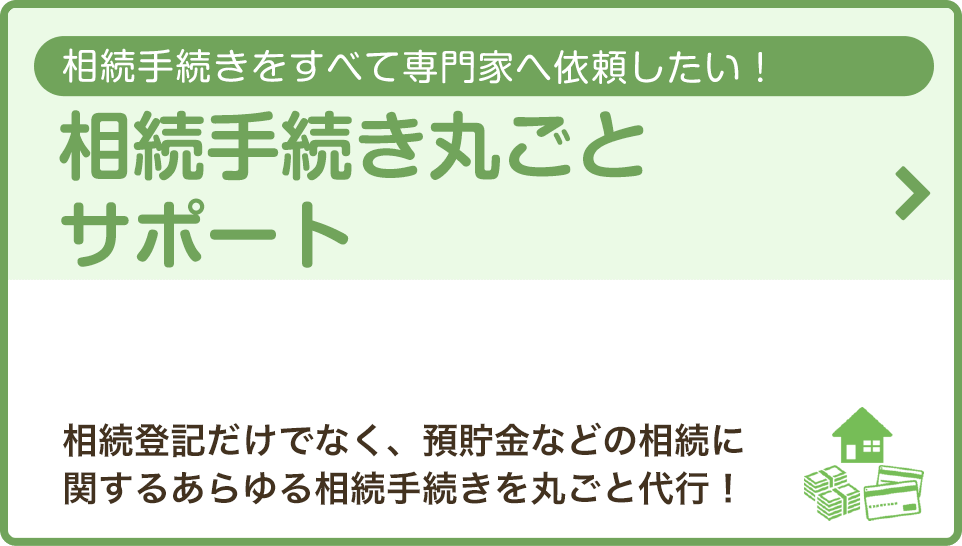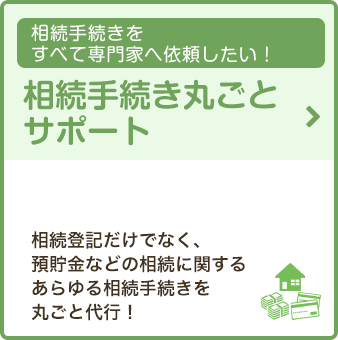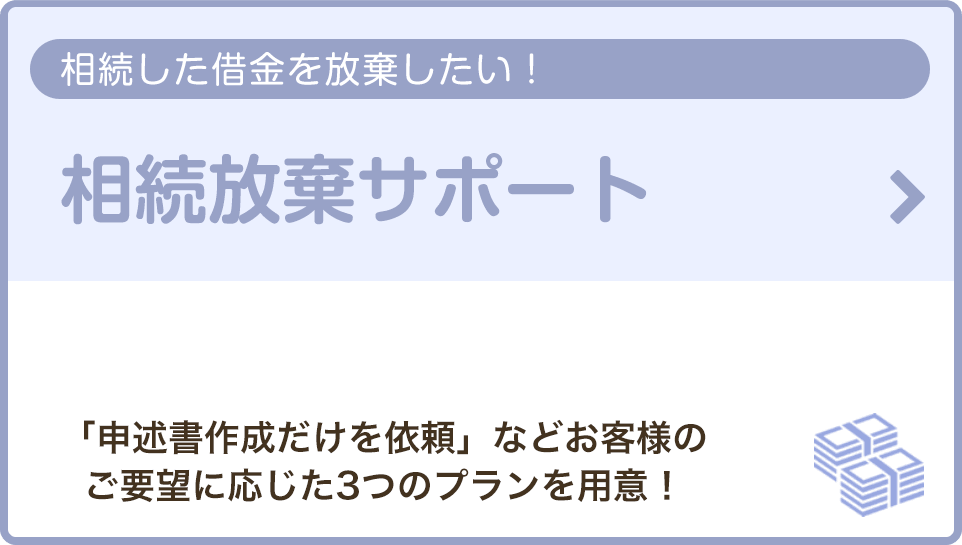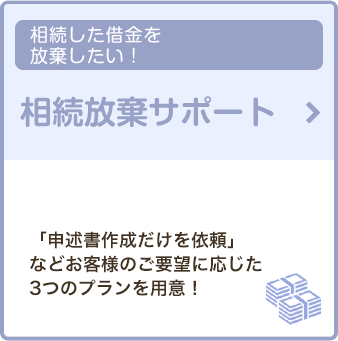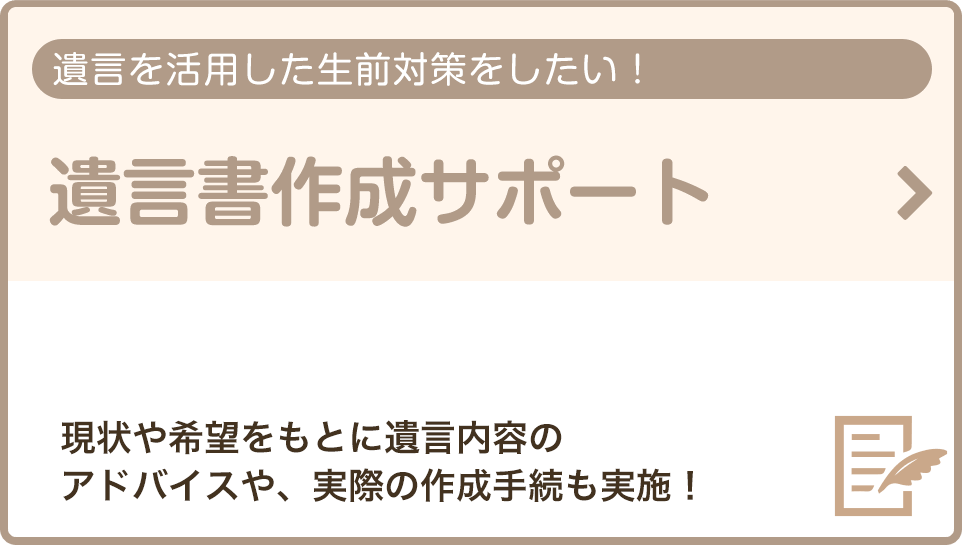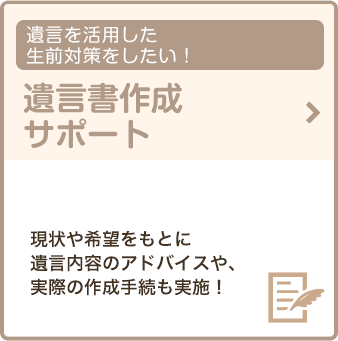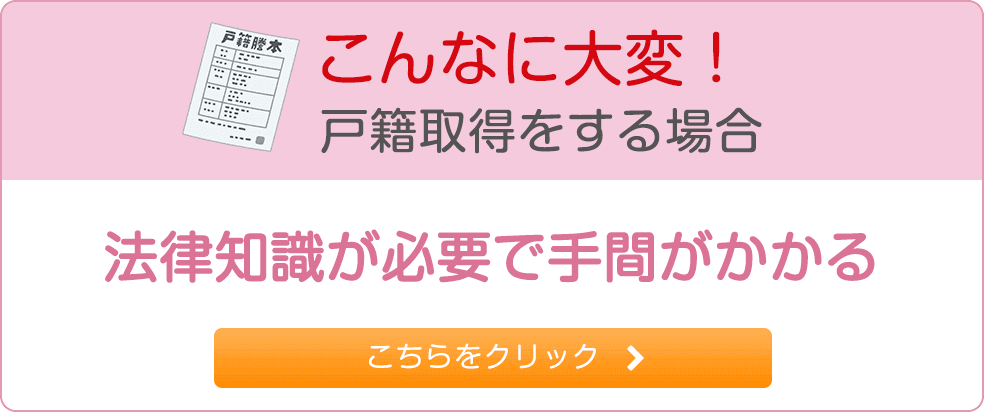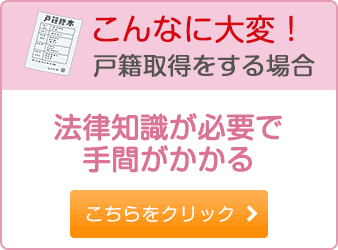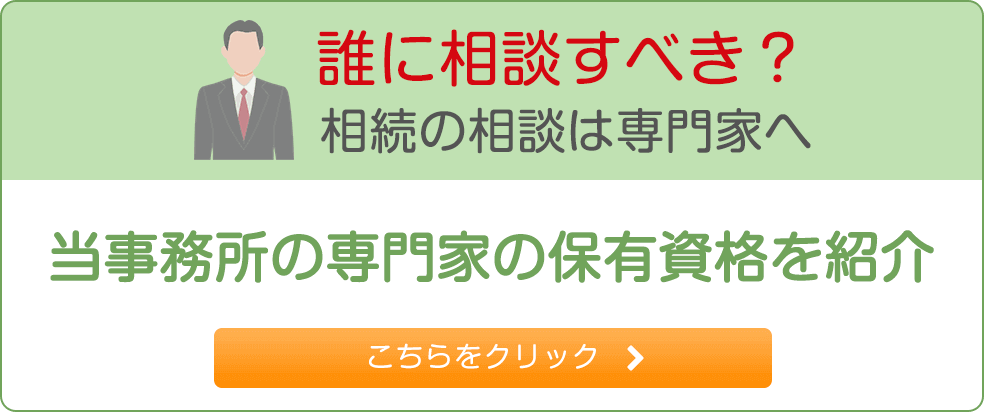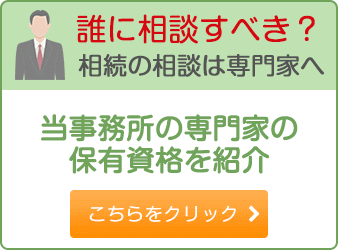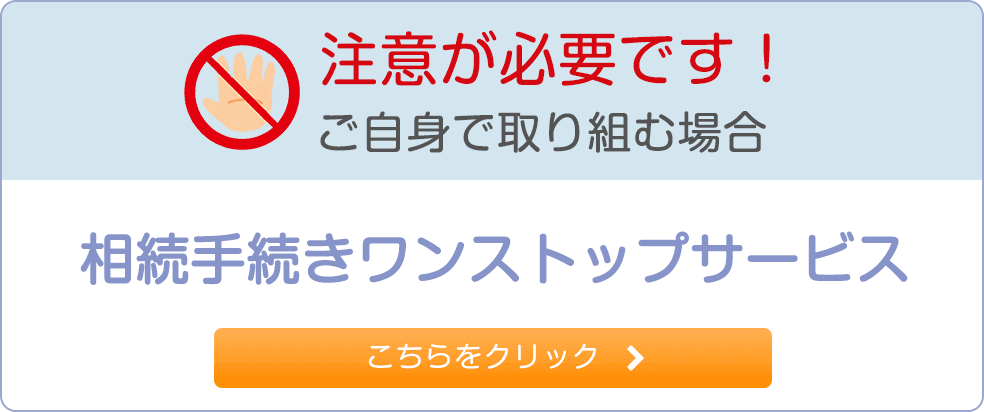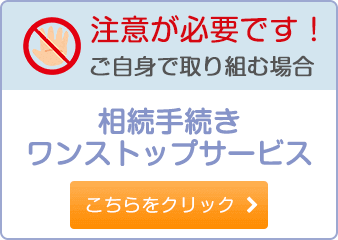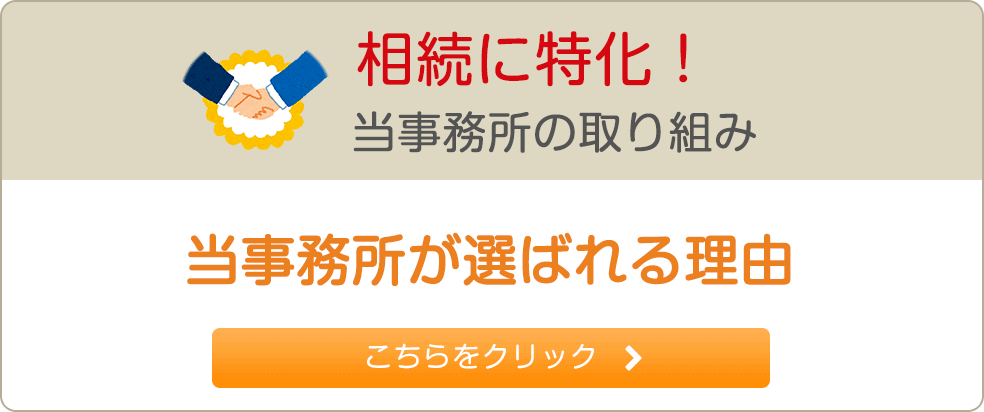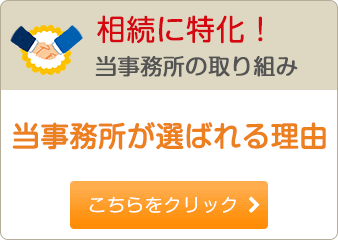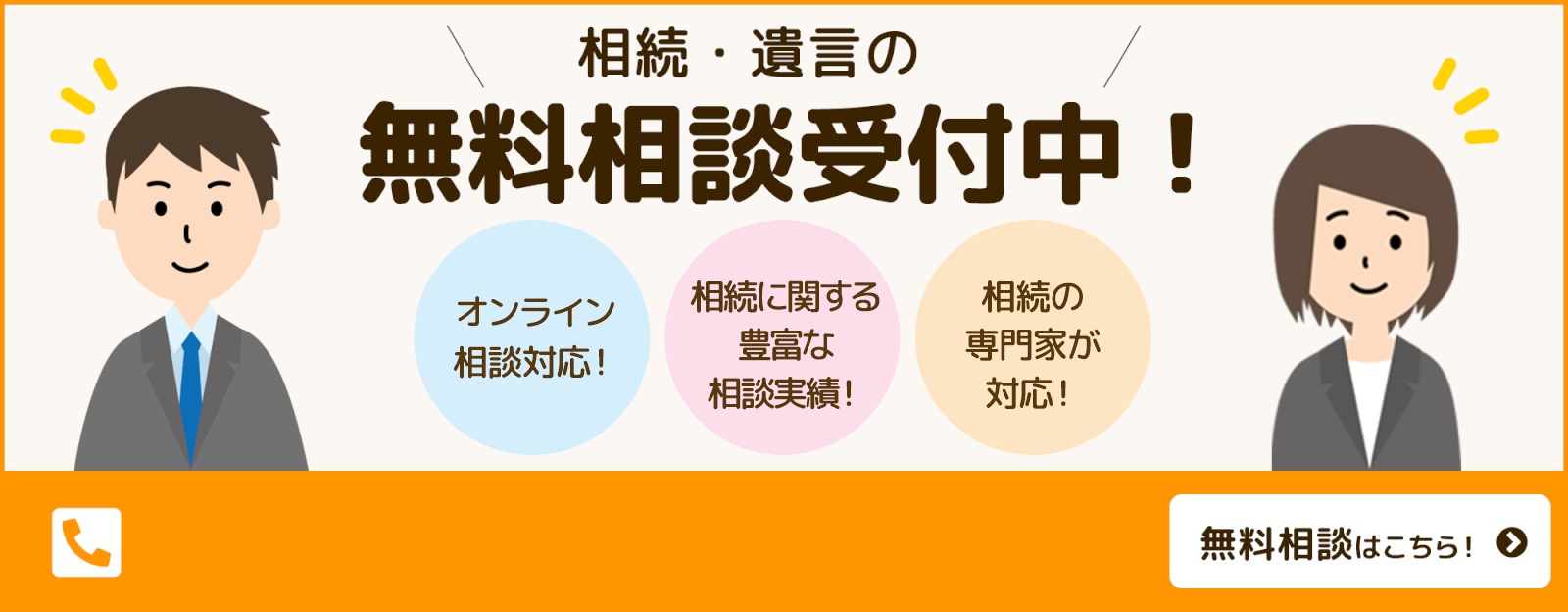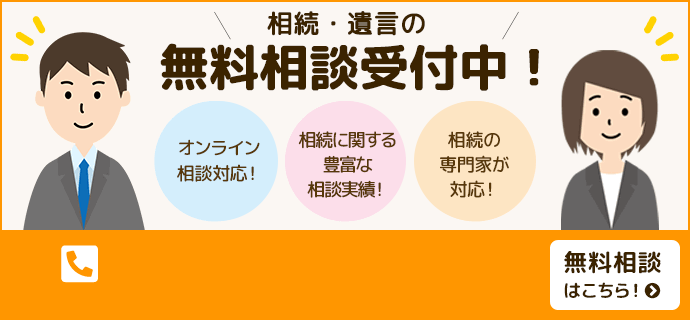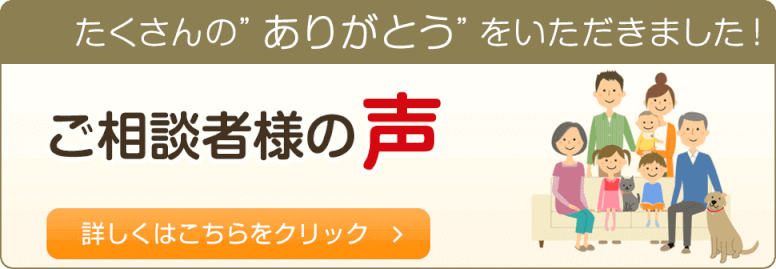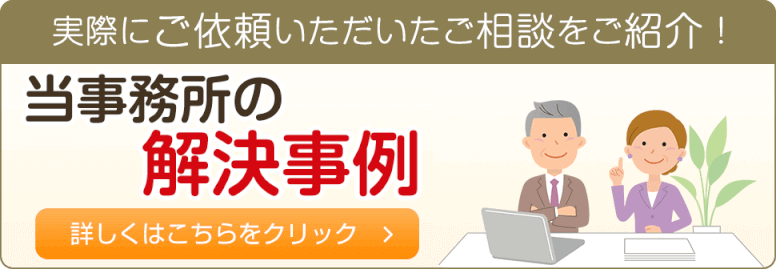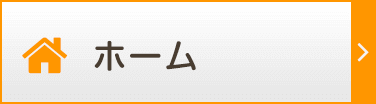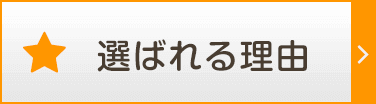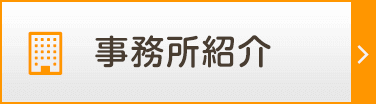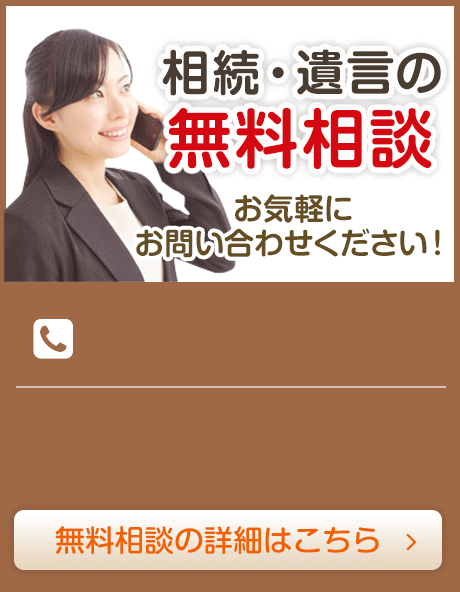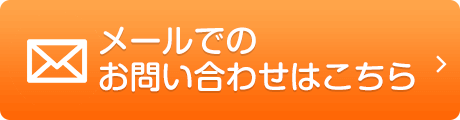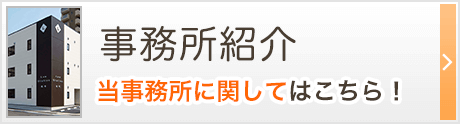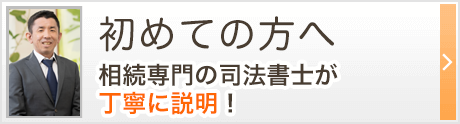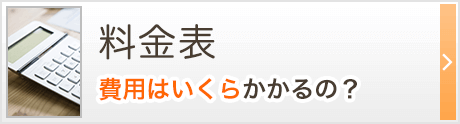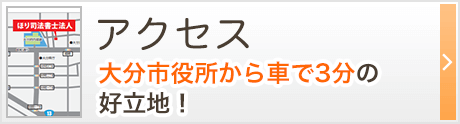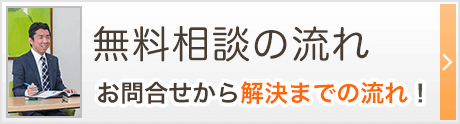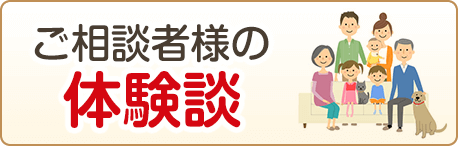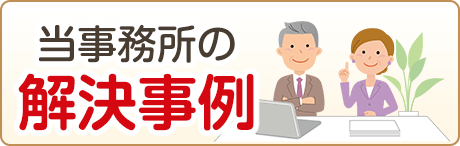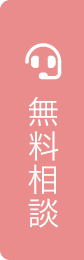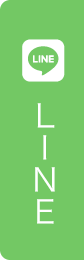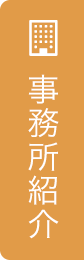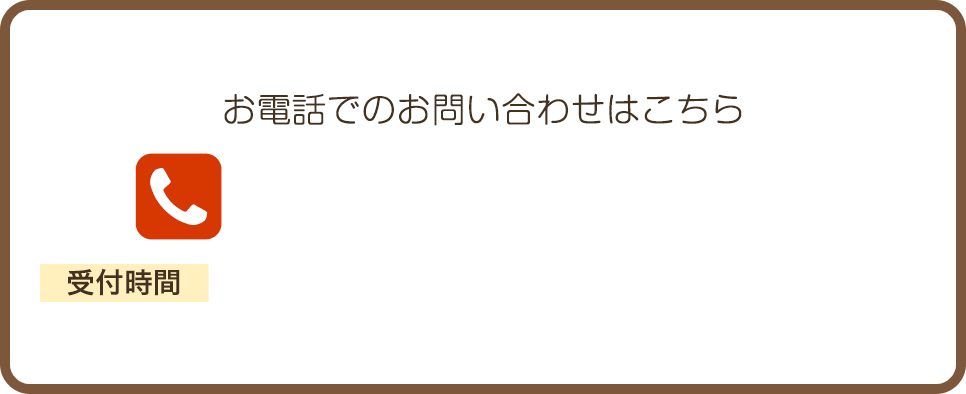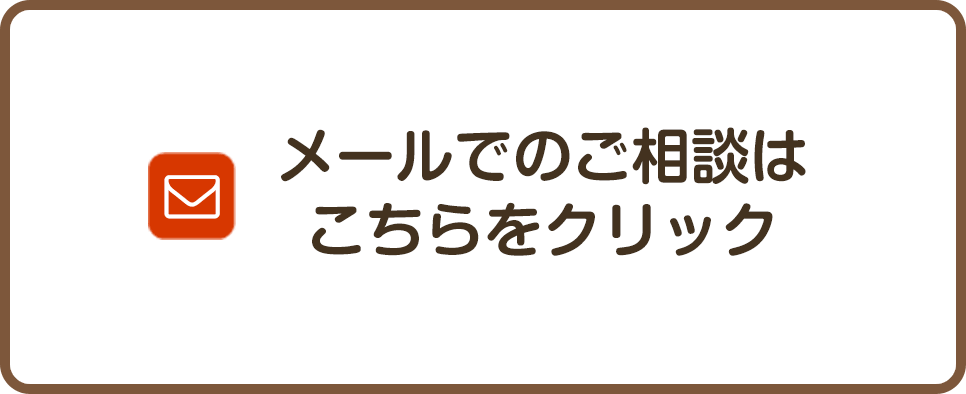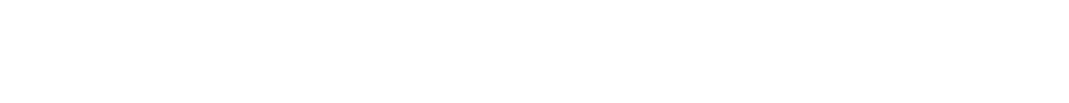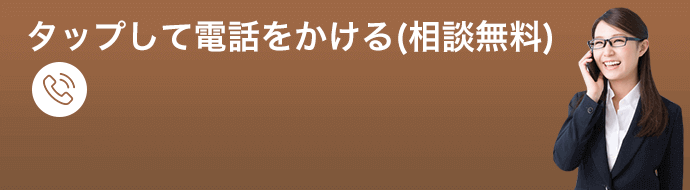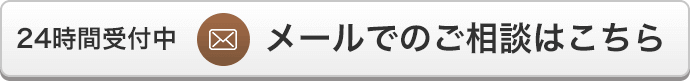【解決事例:残された家族を守る遺言の力】連絡が取れない前妻の子どもがいる場合の相続
- 2025.07.31
目次
お客様のご状況

相談者
今回ご相談にいらしたのは、大分市在住の70代男性、Aさんでした。
奥様と二人暮らしで、お子さんはいらっしゃいません。しかし、Aさんには前妻との間にお子さんが一人いらっしゃいました。
相談内容
Aさんのご相談は、「もし自分に何かあった場合、今の妻が困らないか不安だ」というものでした。
前妻のお子さんとはAさんが再婚して以来、30年近く音信不通の状態が続いており、どこで何をされているのか全く分からないとのこと。
現在の奥様はAさんにとって再婚相手であり、前妻のお子さんとは面識も交流もありません。
Aさんの財産は、ご自宅の土地と建物、そして預貯金が少々。それらを全て現在の奥様に残したいと考えていらっしゃいました。
しかし、前妻のお子さんがいることで、相続が複雑になるのではないかと懸念されていました。
相談の背景
Aさんがご相談にいらしたきっかけは、ご友人との会話だったそうです。
ご友人が相続で揉めたという話を聞き、ご自身ももしものことがあった時に、現在の奥様が大変な思いをするのではないかと心配になったとのことでした。
特に、音信不通の前妻のお子さんがいるという特殊な状況が、Aさんを不安にさせていたようでした。
「今の妻には苦労をかけたくない。これまで一緒に歩んできた妻が、安心して残りの人生を送れるようにしてあげたい」というAさんの強い思いが伝わってきました。
具体的な問題点
遺言がなかった場合に起こりうるトラブル
もしAさんが遺言書を残さずに亡くなった場合、どのようなことが起こるでしょうか?
まず、日本の民法では、配偶者と子どもが相続人となります。
この場合、現在の奥様と、音信不通の前妻のお子さんの両方が法定相続人となります。
法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1となりますので、Aさんの財産の半分は前妻のお子さんに相続されることになります。
しかし、前妻のお子さんとは長年音信不通です。
連絡先も不明なため、まずはそのお子さんの所在を探し出すことから始めなければなりません。
戸籍をたどって住所を特定し、連絡を取ろうと試みることになりますが、これには相当な時間と労力がかかります。
仮に連絡が取れたとしても、面識のない相続人との間で遺産分割協議を行うのは非常に困難が予想されます。
Aさんの現在の奥様は、「財産はすべて自分に」というAさんの意思を尊重したいと願っても、前妻のお子さんには法的に認められた相続分があるため、その意思を一方的に押し通すことはできません。
もし前妻のお子さんが遺産分割協議に応じない場合や、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判といった複雑な手続きに移行せざるを得なくなります。
そうなると、解決までに数年かかることも珍しくなく、精神的な負担はもちろん、弁護士費用などの金銭的な負担も大きくなってしまいます。
特に、現在の奥様は高齢であり、このような負担は計り知れないものとなるでしょう。
トラブル解決するためには複雑な手続きが…
遺言書がない状況で、音信不通の相続人がいる場合の相続手続きは、想像以上に複雑です。
まず、相続人を確定するために、Aさんの出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
これにより、前妻のお子さんが存在することが確認できます。次に、そのお子さんの現在の戸籍謄本や住民票(もしくは戸籍の附票)などを取得し、連絡先を特定しなければなりません。
もし現在の住所が分からない場合は、過去の住所地をたどったり、親族に協力を仰いだりするなど、さらに手間がかかることになります。
連絡先が判明したとしても、相手が相続放棄をしてくれるとは限りませんし、遺産分割協議に応じてくれる保証もありません。
仮に話し合いがまとまらなかった場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。調停でも解決しない場合は、審判へと移行し、最終的には裁判所が遺産分割の方法を決定することになります。
これらの手続きは、すべて法律の専門知識が必要とされ、多くの書類作成や提出期限の管理なども伴います。
普段法律に触れることのない一般の方にとって、これらすべてを自分で行うのは非常に困難で、心身ともに疲弊してしまうことが容易に想像できます。
当事務所からのご提案
Aさんのご相談をお受けし、私はまず、現在の状況とAさんの「妻に財産を全て残したい」という明確なご意思を丁寧にヒアリングしました。
その上で、最も確実かつ円満にAさんの願いを実現する方法として、公正証書遺言の作成をご提案しました。
当初、Aさんは「遺言なんて大げさなもの」と感じていらっしゃいましたが、音信不通の相続人がいる状況で遺言がない場合に起こりうる具体的なトラブルや、奥様が直面するであろう困難について、専門家として分かりやすくご説明しました。
特に、「遺言書があれば、前妻のお子さんの協力を得ることなく、奥様単独で相続手続きを進めることができる」という点を強くお伝えをいたしました。
また、Aさんの前妻のお子様には、法的に**遺留分(いりゅうぶん)という権利があることも丁寧にご説明しました。
遺留分とは、一定の法定相続人に対して、相続財産のうち法律で保証された最低限の取り分のことです。
Aさんの場合、お子さんには法定相続分の半分(全体の4分の1)**が遺留分として認められます。
遺言によって奥様にすべての財産を相続させたとしても、前妻のお子さんが遺留分を主張した場合、奥様はその分を現金で支払わなければならない可能性があることをお伝えしました。
しかし、**遺留分は、請求しなければ発生しない権利です。
**音信不通のお子様が遺留分を知り、請求してくる可能性はゼロではありませんが、遺言書を作成することで、少なくとも遺産分割協議の必要性はなくなり、奥様が財産を独り占めできる可能性が高まります。
また、万が一遺留分侵害額請求がなされた場合でも、その時の対応についても事前にシミュレーションし、奥様が過度な負担を負わないための対策についてもアドバイスをさせていただきました。
Aさんは、ご自身の死後に奥様が複雑な手続きで苦労する姿を想像し、遺言の必要性を強く認識されました。そして、最も安全で確実な公正証書遺言の作成を決断されました。
私の方では、まずAさんの財産状況と家族関係を詳細に把握し、遺言の内容について具体的なアドバイスをさせていただきました。
Aさんのご希望通り、すべての財産を現在の奥様に「相続させる」という内容で、法的に有効かつ誤解の生じない文言を作成しました。
次に、公正証書遺言作成のために必要な書類(戸籍謄本、住民票、不動産の登記簿謄本など)の収集をサポートしました。
Aさんはご高齢のため、役所での手続きが大変だと感じていらっしゃいましたが、私が手続きを代行し、スムーズに書類を揃えることができました。
その後、公証役場との連絡調整を行い、遺言書作成の予約を取り付け、当日は私も立ち会いました。
公証人による遺言内容の確認や意思確認の際も、Aさんが安心して手続きを進められるよう、そばでサポートさせていただきました。
さらに、Aさんには、遺言書作成後も、万が一の際に備えて遺言執行者を指定することの重要性も助言しました。
遺言執行者を指定することで、Aさん亡き後も奥様が一人で相続手続きに奔走することなく、スムーズに遺言内容を実現できることをお伝えしました。
この場合は、司法書士である私が遺言執行者となることも可能である旨もご説明し、Aさんには非常に安心していただけました。
当事務所のサポート結果
公正証書遺言を作成し終えたAさんの表情は、ご相談にいらした時とは別人のようでした。
長年抱えていた奥様への不安が解消され、心から安堵されているのが伝わってきました。
「これで、もしものことがあっても、妻は困らないだろう。遺留分のことまで教えてもらって、万が一の場合にも備えられた。本当に安心したよ。先生に相談してよかった。」
Aさんのこの言葉に、私も深く感動しました。
遺言書は単なる書類ではなく、残される家族へのAさんの深い愛情と、安心して生きてほしいという願いが形になったものです。
この事例を通じて、私は改めて司法書士として、お客様の不安を解消し、未来への安心を提供できることの喜びを感じました。
この事例からお伝えしたいこと
このAさんの事例から、読者の皆様に最もお伝えしたい教訓は、**「遺言書は残された大切な人を守るための、最も有効な手段である」**ということです。
特に、以下のような状況に当てはまる方は、遺言書の作成を真剣に検討していただきたいと思います。
- 前妻(前夫)との間にお子さんがいる方
- お子さんがいないご夫婦
- 相続人の中に連絡が取れない方がいる方
- 特定の財産を特定の誰かに残したいと考えている方
- 内縁の妻(夫)や、事実婚のパートナーがいる方
遺言書がない場合、法律で定められた相続人が遺産分割協議を行うことになります。
しかし、今回のAさんのように、音信不通の相続人がいる場合は、その所在を突き止めるだけでも大変な労力と時間がかかります。
さらに、見ず知らずの相続人と遺産分割について交渉するのは、精神的にも大きな負担となります。
最悪の場合、家庭裁判所での調停や審判に発展し、時間も費用もかかることになります。
また、遺言書を作成しても、遺留分という権利が存在することも忘れてはなりません。
特定の相続人(兄弟姉妹を除く配偶者、子、直系尊属など)には、最低限の遺産を受け取る権利が法律で保障されています。
遺言で特定の相続人に全ての財産を相続させると定めても、遺留分を持つ相続人から請求があった場合、その権利を侵害している分については金銭で支払わなければならない可能性があります。
しかし、遺留分は、あくまで請求があった場合にのみ発生する権利であり、遺言書がない場合に比べれば、残された家族の負担は格段に少なくなります。
そして、遺言書があれば、こうした複雑な手続きやトラブルを未然に防ぎ、ご自身の意思を明確に、そして確実に実現することができます。
遺言書は、残されたご家族が安心して相続手続きを進められるようにするための、いわば「道しるべ」となるのです。
遺言で実現できること
このコラムで皆様に最も強くお伝えしたいのは、遺言の必要性です。
「うちは家族仲が良いから大丈夫」「財産が少ないから関係ない」「まだ若いから先のこと」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続はいつ、誰にでも起こりうる問題です。そして、「家族仲が良い」からこそ、遺言がないことで思いがけないトラブルに発展するケースも少なくありません。
遺言は、ご自身の死後の財産の行き先を決めるとともに、残されたご家族が争うことなく、円満に相続手続きを進められるようにするための、最後のメッセージです。
特に、法定相続人が複数いて、その中に音信不通の人がいる、特定の財産を特定の相続人に渡したい、といった明確な意思がある場合は、遺言書がないことで、ご自身の思いとは全く違う結果になる可能性が高いです。
遺留分を考慮しつつも、遺言で意思表示をすることが、トラブル回避の第一歩となります。
私たちは、**大分で長年、相続や遺言に関するご相談を数多くお受けしてきました。
**お客様それぞれの状況に合わせた最適な解決策をご提案し、安心して未来を迎えられるようサポートしています。相続の準備は、決して「縁起でもないこと」ではありません。それは、大切な人への究極の愛情表現なのです。
遺言について
遺言のメリット
遺言書を作成することには、多くのメリットがあります。
自分の意思を明確にできる
誰にどの財産をどれだけ渡したいのか、自分の最終的な意思を明確にすることができます。こ
れにより、法定相続分にとらわれず、ご自身の思い通りの財産分配が可能です。
相続争いを防ぐ
遺言書があれば、遺産分割協議が不要になるか、あるいはその範囲を限定することができます。
これにより、相続人同士の無用な争いを防ぎ、円満な相続を実現できます。
特に、前妻のお子様がいる場合や、お子様のいないご夫婦の場合には、遺言の有無が残された配偶者の生活に大きく影響します。
遺留分がある場合でも、遺言で意思を示しておくことで、紛争の長期化を防ぐ効果があります。
相続手続きをスムーズに進められる
遺言書があることで、相続人による手続きが簡素化され、時間と手間を大幅に削減できます。音信不通の相続人がいても、遺言があればその人抜きで手続きを進められる場合もあります。
相続人以外にも財産を渡せる
お世話になった方や、団体・法人など、法定相続人ではない方にも財産を渡すことができます。
特定の人に多く財産を残せる
特定の相続人に多くの財産を残したい場合でも、遺言があればその意思を実現できます。例えば、介護をしてくれた子に多く残したい、といったケースです。
相続税対策になる可能性もある
遺言の内容によっては、相続税の負担を軽減できるケースもあります。
遺言がない場合のデメリット
一方、遺言書がない場合には、以下のようなデメリットが生じる可能性があります。
遺産分割協議が必要となる
相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意する必要があります。相続人全員の同意がなければ、遺産分割はできません。
相続争いに発展するリスクが高い
相続人それぞれの主張がぶつかり、意見がまとまらず、争いに発展する可能性が高まります。
相続手続きが複雑化・長期化する
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停や審判に移行し、解決までに数年かかることもあります。その間、預貯金の引き出しや不動産の売却などができず、生活に支障が出ることもあります。
望まない相手にも財産が渡る可能性
今回の事例のように、長年音信不通の親族など、望まない相手にも法定相続分に応じて財産が渡ってしまうことがあります。また、特定の相続人が遺留分を超えて遺産を受け取る場合でも、遺言がないとそれが実現できません。
内縁の妻(夫)などが財産を受け取れない
法律上の婚姻関係がないパートナーには、遺言がない限り相続権はありません。
皆様へのメッセージ
大分にお住まいの皆様、そして相続や遺言についてお考えの皆様へ。
「相続」は、誰もが直面しうるけれど、なかなか準備ができない、という方も多いのではないでしょうか。
特に、「遺言」と聞くと、まだ早い、自分には関係ない、と思われるかもしれません。
しかし、今回のAさんのように、ご家族の状況によっては、遺言の有無が、残された方々の人生に大きな影響を与えることがあります。
私たち司法書士は、法律の専門家として、皆様一人ひとりのご状況に寄り添い、最適な相続・遺言のプランをご提案します。
**遺留分に関するご心配も含め、複雑な法律関係を分かりやすく解説し、**戸籍の収集から遺言書の作成、さらには遺言執行まで、複雑な手続きを分かりやすくサポートし、皆様が安心して未来を迎えられるようお手伝いいたします。
大切なご家族が、もしもの時に困らないように。
そして、ご自身の「こうしたい」という思いを、確実に未来へと繋いでいくために。
大分県内で相続や遺言についてお悩みでしたら、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
初回のご相談は無料です。私たちは、皆様の不安を解消し、安心して次の一歩を踏み出せるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
お電話、またはメールにて、お気軽にお問い合わせください。
相続・遺言に関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは 097-538-1418 になります。お気軽にご相談ください。
メールの場合は下記よりお問い合わせください
下記項目にご入力後、一番下の「この内容で送信する」ボタンをクリックしてください。
※は入力必須項目です