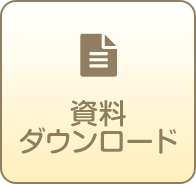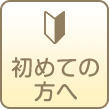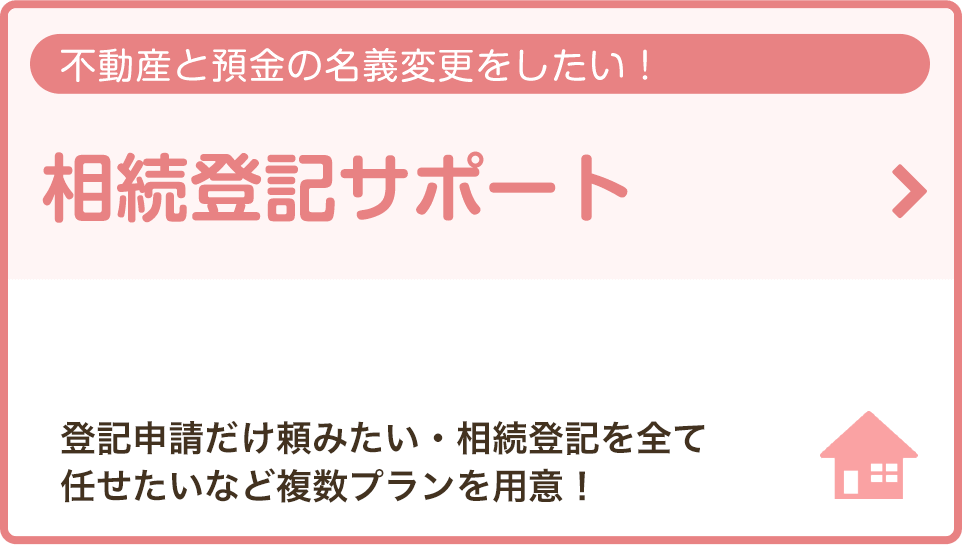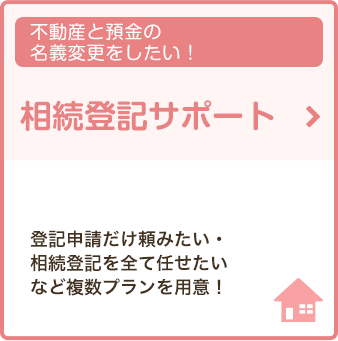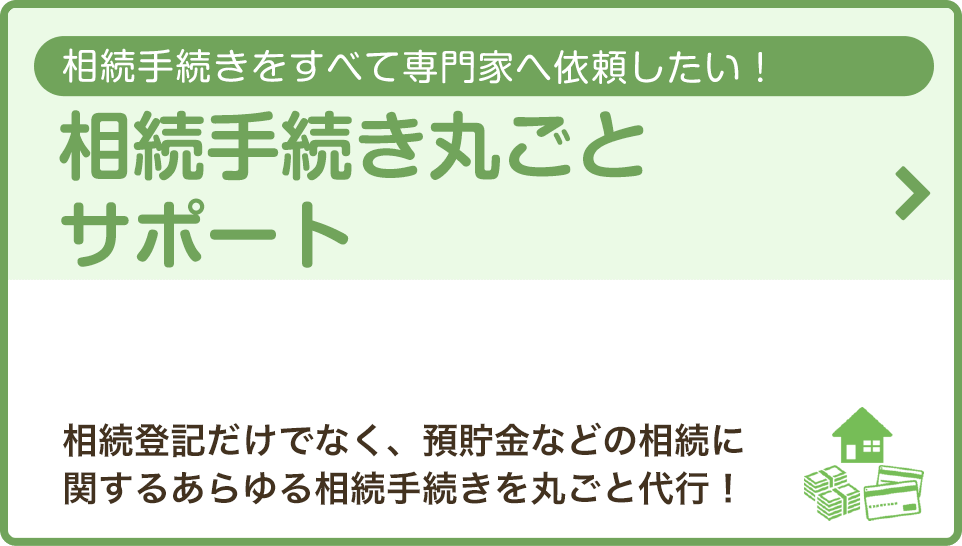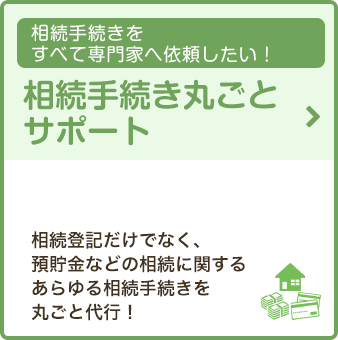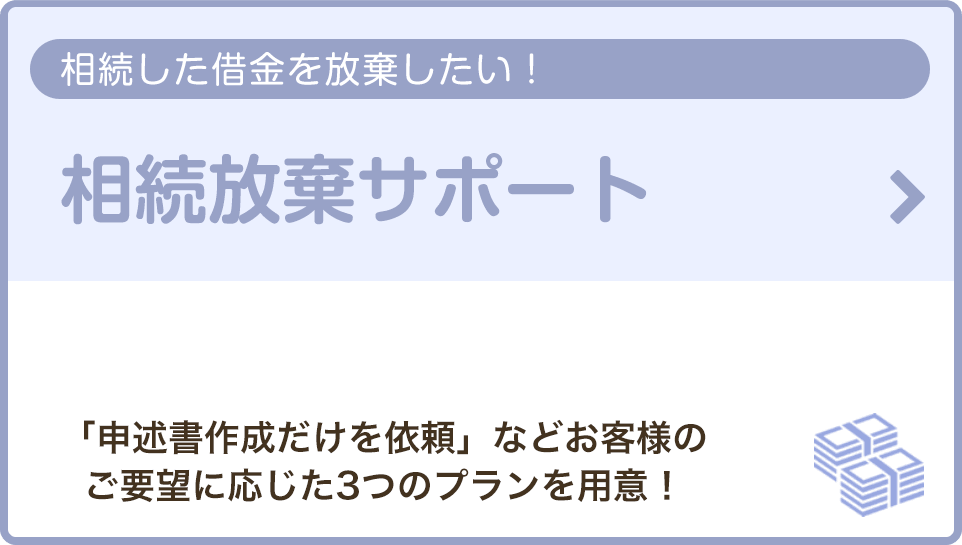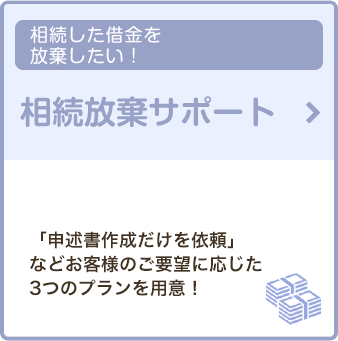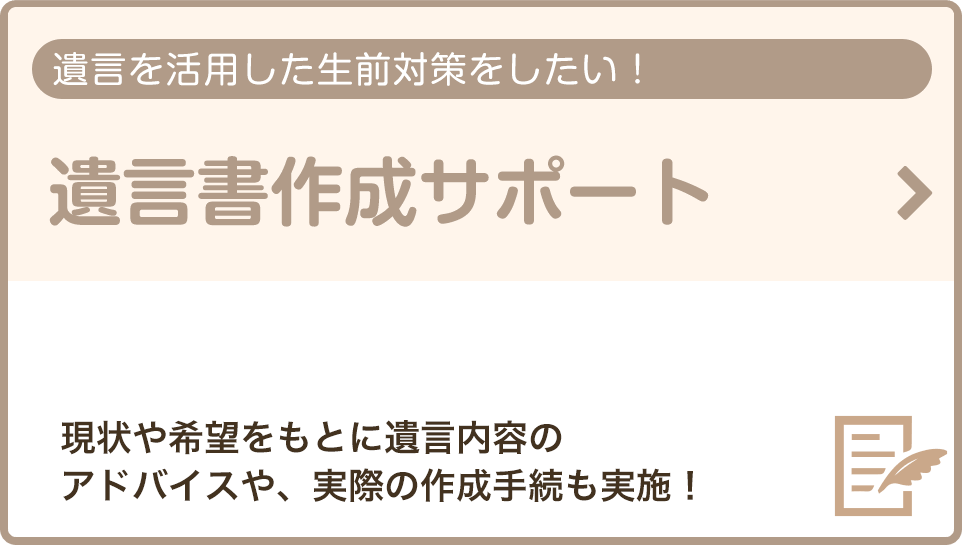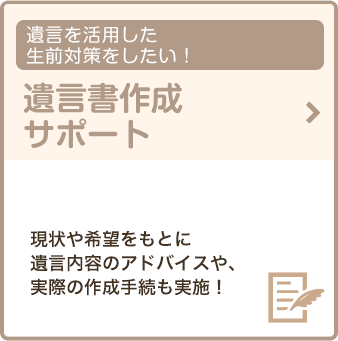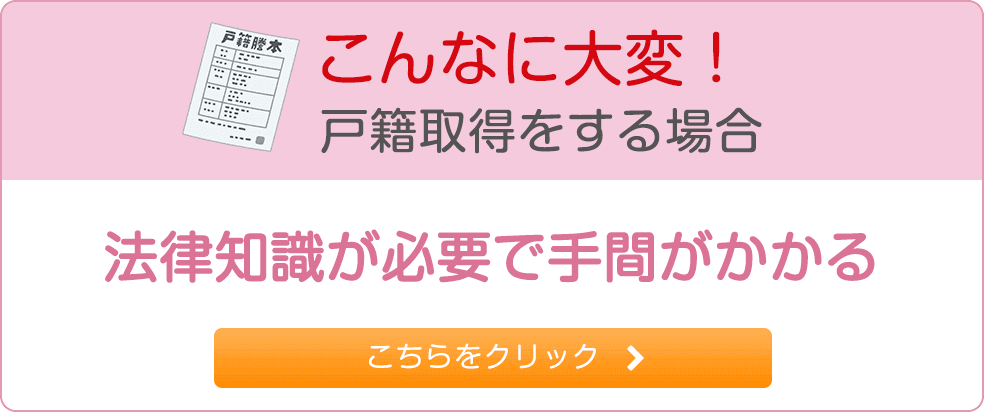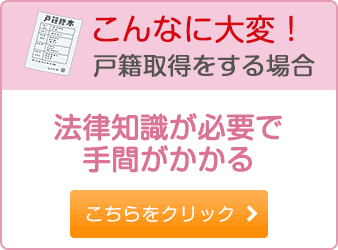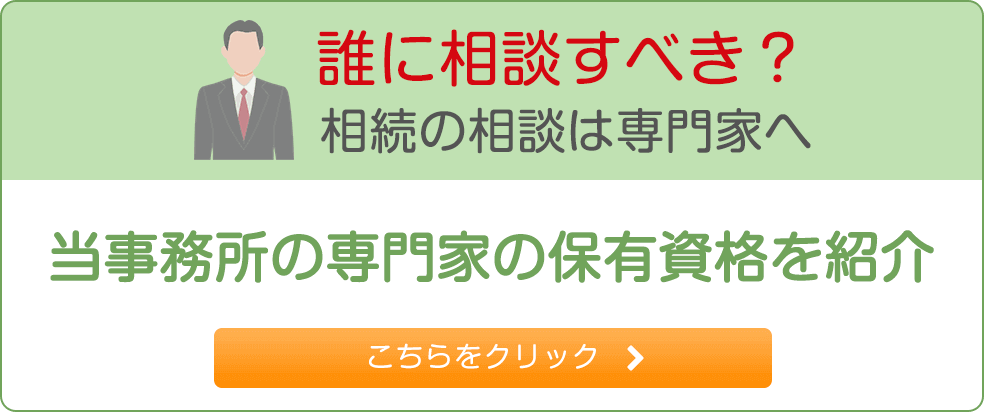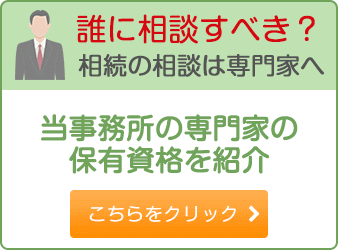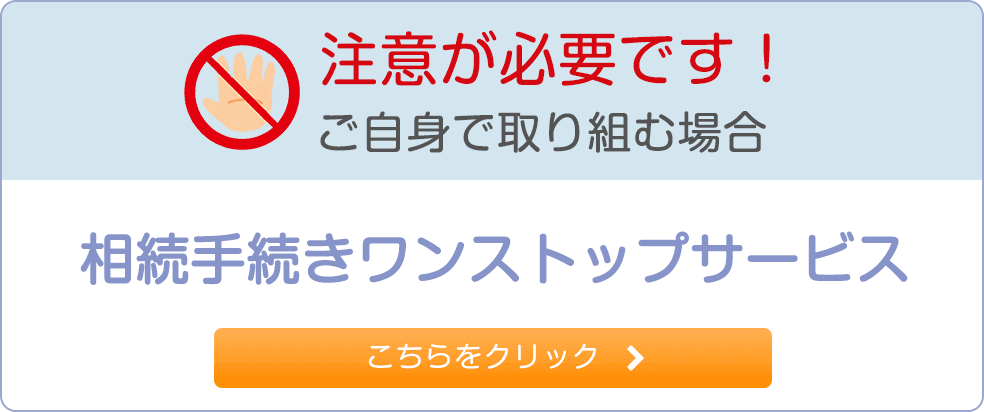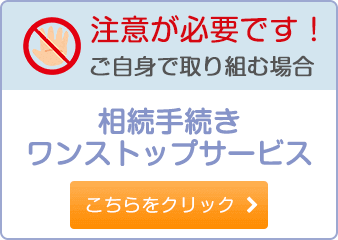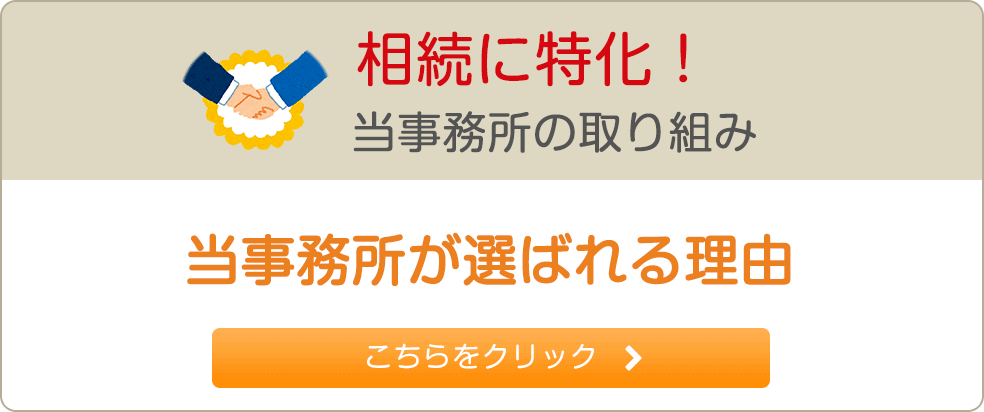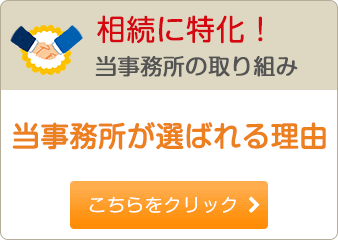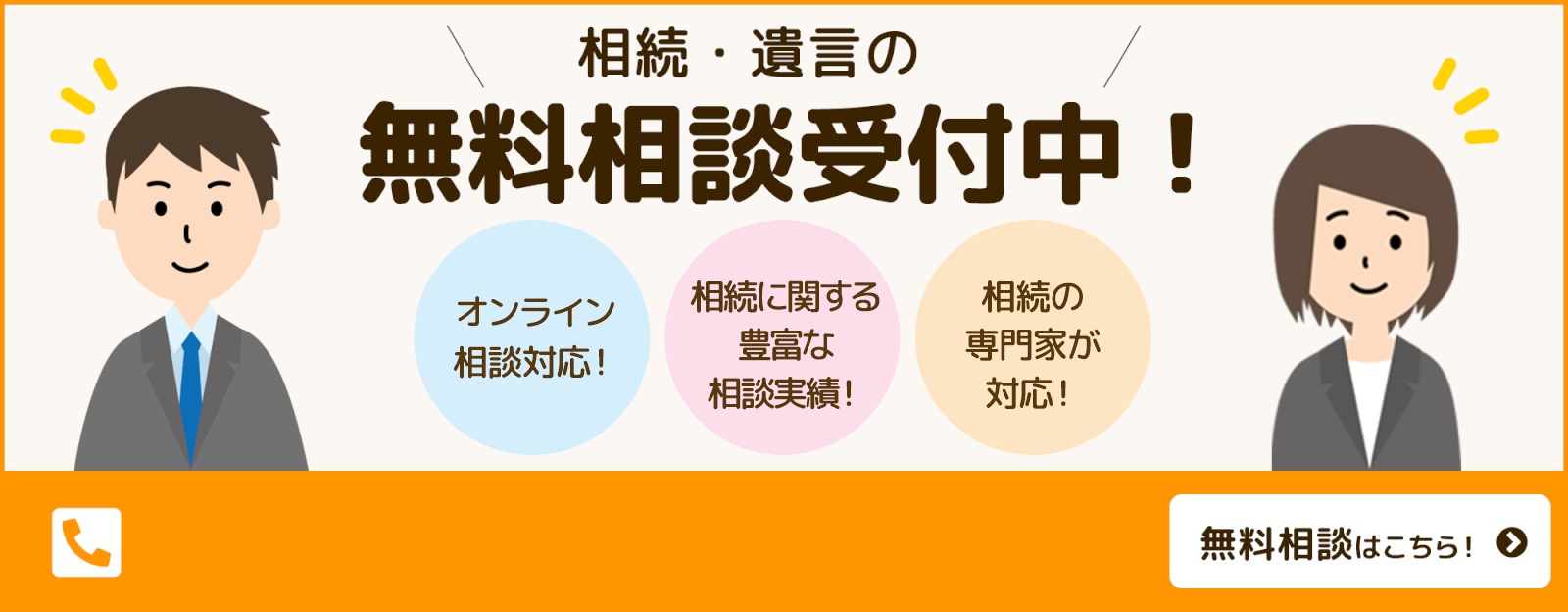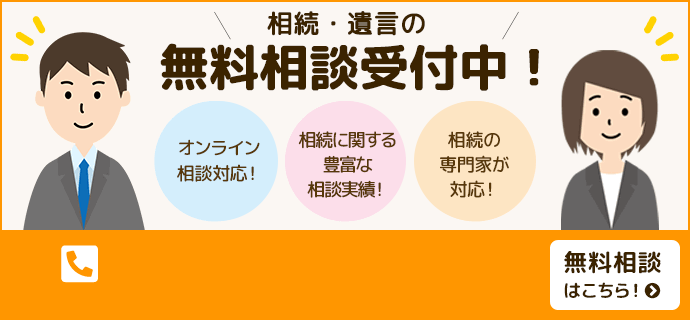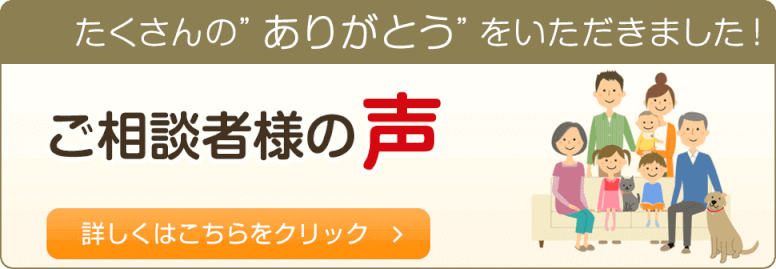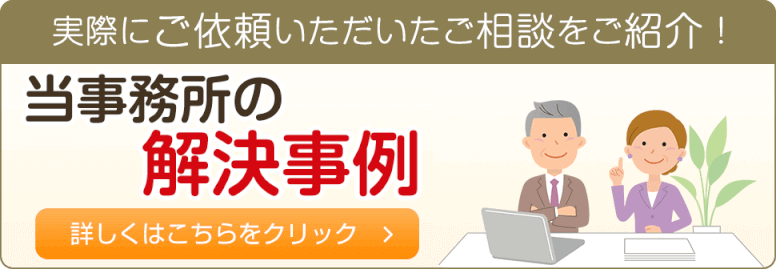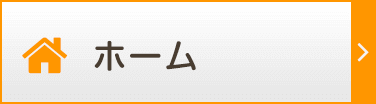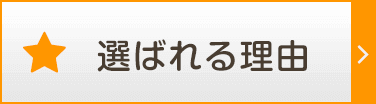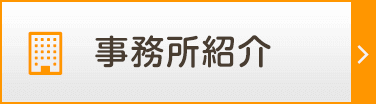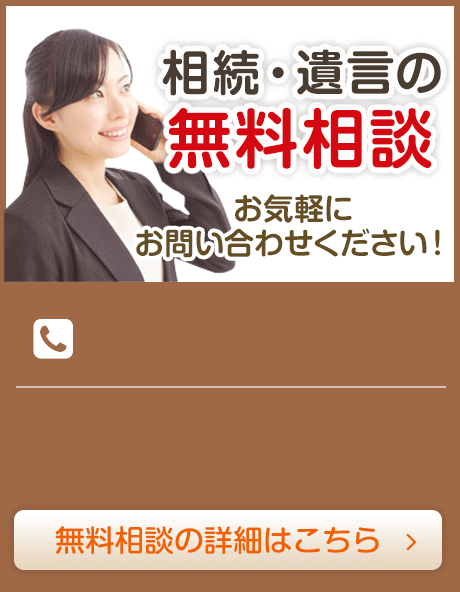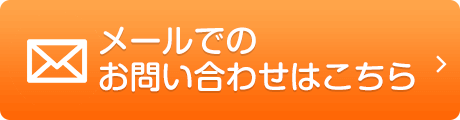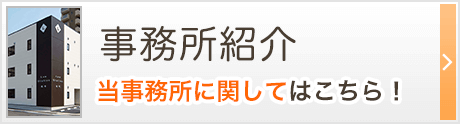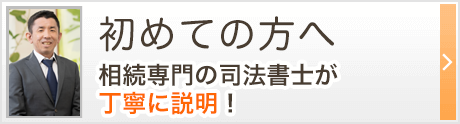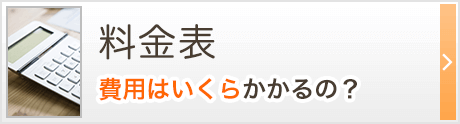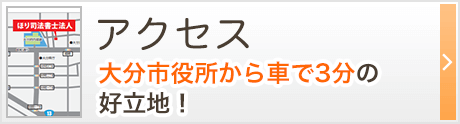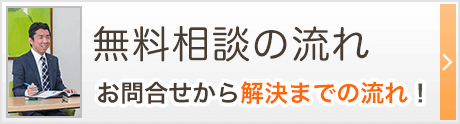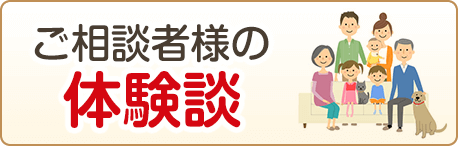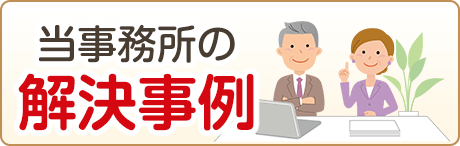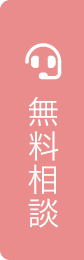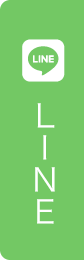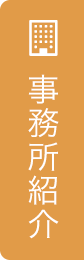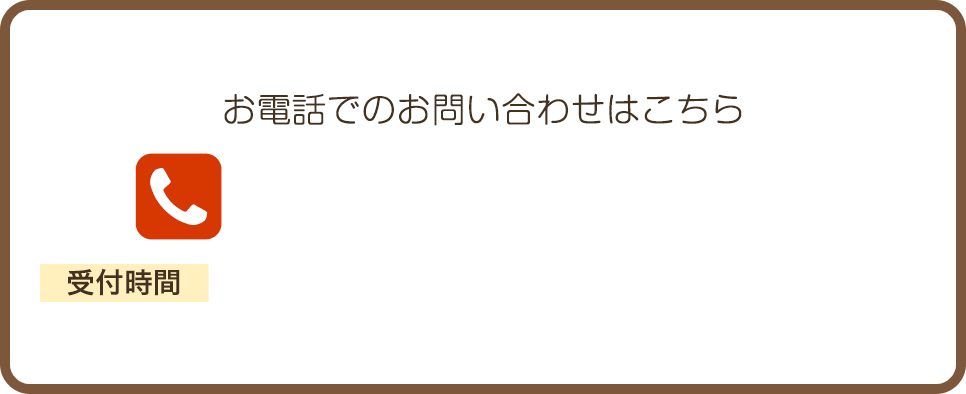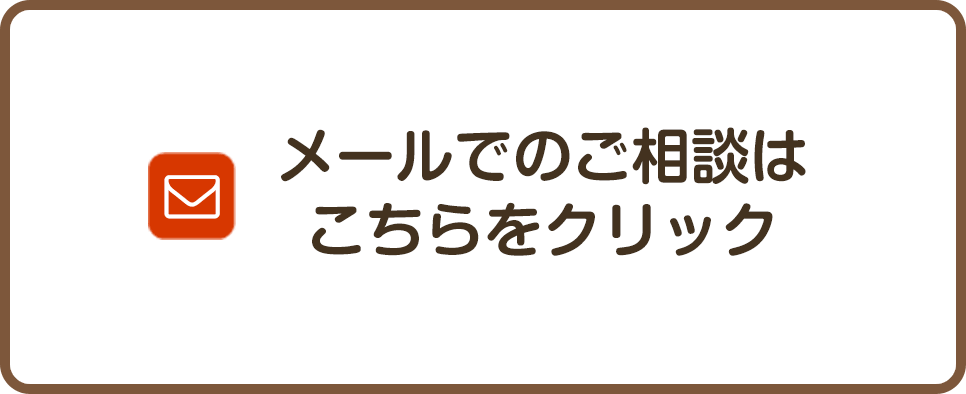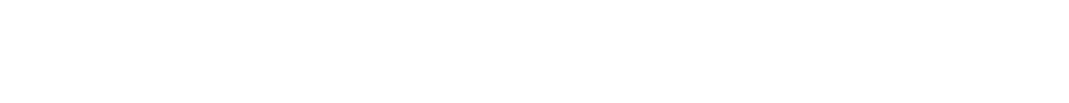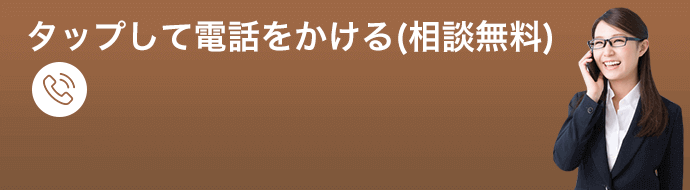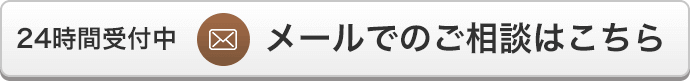【司法書士が解説】音信不通の長男に財産を渡したくない…80代男性が「遺言書」で実現した、たった一人の長女への想い|大分相続・財産管理センター
- 2025.09.09
大分で相続・遺言のご相談を承っております、司法書士の堀です。
司法書士として、これまで数多くの相続手続きをお手伝いする中で、「もっと早くご相談いただけていれば…」と感じる場面に何度も遭遇してきました。
特に、ご家族の関係が複雑なケースほど、事前の準備、すなわち「遺言書」の有無が、残されたご家族の未来を大きく左右します。
今回は、ご家族への想いを法的に確実な形にすることで、長年の不安を解消された、大分市在住Aさんの事例をご紹介します。
このコラムが、同じようなお悩みを抱える皆様の、一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
1. ご相談の状況
相談者: Aさん(80代・男性)
ご家族: 既に他界された奥様、同居して身の回りの世話をしてくれる長女(50代)、30年以上音信不通の長男(60代)
居住地: 大分市
主な財産: ご自宅の土地・建物(Aさん名義)、預貯金
ご相談内容
ある日、私の事務所に、娘さんに付き添われてAさんがお見えになりました。
「先生、もし私に万が一のことがあったら、この子(長女)にすべての手続きを任せることになります。
ですが、実は30年以上も音信不通の長男がいるのです。あの子に迷惑をかけずに、私が亡くなった後のことをすべて済ませることはできないでしょうか。」
Aさんは、長年連れ添った奥様を数年前に亡くされ、以降、身の回りのことはすべて長女のBさんが担っていました。
Aさんとしては、ご自身の財産、特に今住んでいる家と土地は、Bさんに残したいと強く願っておられました。
ご相談の背景
Aさんの長男は、若い頃に些細なことで口論となり家を飛び出して以来、全く連絡が取れない状態でした。
風の噂で遠方で暮らしているらしいとは聞いたものの、今どこで何をしているのか、生きているのかどうかさえ定かではありませんでした。
Aさんの心配は、「自分が亡くなった後、法律上は長男にも相続権があるはず。
そうなると、Bがたった一人で、何十年も会っていない兄を探し出し、財産の分け方を話し合う『遺産分割協議』をしなければならないのではないか」という点にありました。
想像するだけで、Bさんに計り知れない負担と精神的苦痛を与えてしまうことに、胸を痛めておられたのです。
「できることなら、私の財産はすべてBに残したい。それが無理でも、とにかくBに面倒な思いはさせたくない」
それがAさんの切なる願いでした。
2. このまま遺言がなかった場合の具体的な問題点
Aさんのご心配は、残念ながら的を射ていました。
もしAさんが遺言書を作成しないまま亡くなられた場合、残されたBさんには、次のような困難が待ち受けていた可能性が非常に高いのです。
① 音信不通の相続人を探し出す、困難な手続き
相続手続きを開始するには、まず「誰が相続人なのか」を確定させる必要があります。
そのためには、Aさんの出生から死亡までのすべての戸籍謄本等を取り寄せ、相続人を確定させます。
その結果、長男が相続人であることが判明すれば、次はその長男の現在の住所を突き止めなければなりません。
戸籍をたどり、戸籍の附票(住所の履歴が記録された書類)を取得していくのですが、転居を繰り返している場合などは、調査が非常に煩雑になり、時間も費用もかかります。
Bさんがお一人でこの作業を行うのは、大変なご負担です。
② 30年ぶりの再会が「争続」の始まりに…
仮に長男の居場所が判明し、連絡が取れたとします。
しかし、30年以上会っていないきょうだいが、いきなり財産の話を円満に進められるでしょうか。
長男が「法律で定められた自分の権利(法定相続分)は主張する」と言った場合、Bさんはそれに応じざるを得ません。
今回のケースでは、長男の法定相続分は全財産の2分の1です。
もし、ご自宅の不動産しかめぼしい財産がない場合、長男の相続分に相当する現金をBさんが用意できなければ、最悪の場合、ご自宅を売却して代金を分けなければならない「換価分割」という事態に陥る可能性すらありました。
思い出の詰まった家を手放し、Bさんご自身の住まいまで失うことになりかねません。
③ 話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所へ
もし当事者間での話し合い(遺産分割協議)がまとまらなければ、家庭裁判所での調停や審判へと移行します。
こうなると、解決までに年単位の時間がかかることも珍しくなく、弁護士費用なども発生します。
何より、肉親同士が裁判所で争うという事実は、Bさんにとって大きな精神的ストレスとなるでしょう。
Aさんが最も望まない「争続」の典型的なパターンです。
3. 司法書士としての提案と解決への道筋
私はAさんとBさんのお話をじっくりと伺い、Aさんの「Bさんに負担をかけず、財産を確実に渡したい」という想いを実現するための最善の方法として、**「公正証書遺言」**の作成をご提案しました。
なぜ「公正証書遺言」なのか
遺言には自分で書く「自筆証書遺言」もありますが、法律で定められた形式を誤ると無効になるリスクや、紛失・改ざんの恐れ、そして亡くなった後に家庭裁判所での「検認」という手続きが必要になるなど、残されたご家族に負担がかかる場合があります。
一方、「公正証書遺言」は、公証役場で公証人と証人2名の立会いのもと作成するため、法的に無効になる心配がほぼなく、原本が公証役場に保管されるため非常に安全で確実です。
また、検認手続きも不要なため、相続開始後、Bさんはスムーズに不動産の名義変更や預貯金の解約手続きを進めることができます。
遺留分にも配慮した、円満な解決策
ここで一つ重要な点があります。たとえ遺言で「全財産を長女Bに相続させる」と書いても、兄弟姉妹以外の相続人には**「遺留分」**という、法律で保障された最低限の取り分を請求する権利があるのです。
このケースでは、長男には法定相続分(1/2)のさらに半分、つまり全財産の1/4の遺留分があります。
もし遺留分を無視した内容の遺言を作成すると、亡くなった後で長男からBさんに対して「遺留分侵害額請求」をされ、金銭トラブルに発展する可能性があります。そこで私は、将来の紛争の芽を完全に摘み取るため、Aさんのご意向を確認した上で、長男から遺留分を請求された場合には長男の遺留分に相当する額を預貯金の中から支払う、という内容を遺言に盛り込むことをご提案しました。
さらに、遺言の最後には**「付言事項」**として、Aさんご自身の言葉でメッセージを残すことをお勧めしました。
「長年にわたり身の回りの世話をしてくれた長女Bに、安心して暮らせる家を残してやりたい。長男には、親として何もしてやれなかったことを申し訳なく思う。どうかこの遺言の内容を理解し、Bと仲良くしてほしい。」
このような想いを綴ることで、単なる財産の分配だけでなく、Aさんの真意が長男にも伝わり、無用な争いを避ける効果が期待できます。
解決後のAさんの声
公証役場での手続きをすべて終え、公正証書遺言の謄本をお渡しした際、Aさんは本当に晴れやかな表情でこうおっしゃいました。
「先生にお願いして、本当によかった。胸のつかえが取れて、これで安心して眠れます。
自分一人ではどうしていいか分からず、ずっと不安な日々を過ごしていました。この遺言があれば、私がいつどうなっても、あの子が困ることはない。そう思うと、心から安堵しました。」
隣にいらしたBさんも、「父の想いが形になって、私も安心しました。これで父の介護に専念できます」と涙ぐんでおられました。
この事例から皆様に学んでいただきたい教訓は、「自分の死後、子供たちが何とかしてくれるだろう」という希望的観測は、時として残された家族に大きな負担を強いる結果になるということです。
そして、家族関係が複雑な方ほど、ご自身の意思を明確に示す「遺言」という名の道しるべを残しておくことが、何よりの愛情表現になるのです。
4. 「遺言」の重要性
今回の事例でもお分かりいただけたように、遺言には大きな力があります。
遺言があることのメリット
「争続」の予防: 誰に何を相続させるか明確にすることで、相続人間の無用な争いを防ぎます。
手続きの円滑化: 遺産分割協議が不要となり、相続手続きがスムーズに進みます。特に公正証書遺言の場合、その効果は絶大です。
想いの実現: 法定相続分とは異なる割合で財産を分配したり、お世話になった方など相続人以外の人に財産を遺したり(遺贈)、ご自身の想いを実現できます。
家族へのメッセージ: 付言事項で、感謝の気持ちや想いを伝えることができます。
遺言がない場合のデメリット
遺産分割協議が必須: 相続人全員での話し合いが必要となり、時間と手間がかかります。
トラブルのリスク: 話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所での調停・審判となり、家族関係に亀裂が入る可能性があります。
手続きの煩雑化: 相続人の中に行方不明者や未成年者、認知症の方がいる場合、手続きはさらに複雑化します。
5. まとめ
今回ご紹介した大分市在住のAさんの事例は、決して特別なものではありません。
音信不通の相続人がいる、特定の子供に多く財産を残したい、内縁の妻やお世話になった人に財産を渡したいなど、ご家庭の事情は様々です。
Aさんは、司法書士という専門家にご相談いただくことで、ご自身の法的な権利と義務(遺留分など)を正確に理解し、長年の悩みであった音信不通の長男への対応も含め、長女Bさんへの想いを「公正証書遺言」という最も確実な形で残すことができました。
これにより、将来起こり得たであろう複雑な相続手続きや親族間の争いを未然に防ぎ、心穏やかな老後を取り戻されたのです。
相続は、誰にでも必ず訪れる、人生の締めくくりに関わる大切な手続きです。
「まだ早い」「うちは財産がないから大丈夫」と思わず、ご自身の想いを確かな形で残すため、そして何より、愛するご家族を守るために、元気なうちにこそ「遺言」の作成をご検討ください。
私たち司法書士は、法律の専門家であると同時に、皆様の想いに寄り添う身近な相談相手です。
大分で相続や遺言について少しでもご不安なことがございましたら、どうぞお一人で悩まず、お気軽にご相談ください。あなたの、そしてご家族の未来のために、最適な解決策を一緒に見つけていきましょう。